苦情学Ⅱ 著:関根眞一

苦情は、発覚した時点が始まりではないという箇所は、もう唖然とする位頭にありませんでした。
お客様は勇気を出して苦情を言うのです。
そして、そこまでの心理を解ろうとしないで、そのお客様の苦情を受け入れることはできません。
提供側の不備が苦情の始まりで、それを解決するには、その物理的な解決が必要条件、お客様の心を汲み取り受容するのが十分条件です。
苦情に対しての提供側の捉え方も教えてくれていますが、
商人の心得としても説得力がある本でした。
【いもたつLife】

苦情は、発覚した時点が始まりではないという箇所は、もう唖然とする位頭にありませんでした。
お客様は勇気を出して苦情を言うのです。
そして、そこまでの心理を解ろうとしないで、そのお客様の苦情を受け入れることはできません。
提供側の不備が苦情の始まりで、それを解決するには、その物理的な解決が必要条件、お客様の心を汲み取り受容するのが十分条件です。
苦情に対しての提供側の捉え方も教えてくれていますが、
商人の心得としても説得力がある本でした。
【いもたつLife】

干し芋を販売していて、ご購入したお客様が何を期待して、
私どもの干し芋を購入してくださっているか、
そんな基本中の基本をわかろうともしていなかった、恥ずかしくなりました。
干し芋自体の品質はもちろん、お客様の期待に応えられるモノなのは当たり前で、
それ以外の販売に関連する付帯すべてが、商品で、そこにもお客様の期待があります。
驕りを正された本でした。
【いもたつLife】

とても楽しい時間でした。
サーカス小屋でのピエロのパフォーマンスを想わせる、4人の役者の演技と演奏、どちらも子供心に返し浮き立たせてくれます。
貧しい家族の父親が悪魔に騙され、娘を奪われそうになります。娘はなんとか悪魔から逃れますが、両腕を切り取られてしまいます。そして旅に出る娘、天使の手助けがあり、ある区にの王様に見初められます。
幸せな日々は束の間、王様は戦争にいきます。その間に王子が生まれます。その便りを王様に出す王妃ですが、その手紙は悪魔によって差し替えられます。
醜い王子が生まれたという偽手紙に惑わされない王様は王妃に返事を書きます。その返事も悪魔は差し替えます。その偽手紙には王子を殺せと書かれていました。
王子と王妃の運命は、という物語です。
テンポが速く、茶化した音楽と演技で子供が観ても面白い劇で、実際親子連れも多く観劇していました。
でも演技のレベルはとても高く、テーマも人の営みが生む人同士の信頼が大きな力にあるという、希望あるものです。
そしてこの劇をみていると、パリの下町で親しい者同士、子供からお年寄りまでが集まり、どこかの庭で和気藹々と演劇を楽しんでいる感覚になりました。
懐かしくなる空間でもありました。
【いもたつLife】

終盤、壮絶な舞台が待っていました。これを毎回やっているかと疑いたくなるほどのパフォーマンスで、特異な表現方法でもありました。
そして、それは物語のどんでん返しからはじまり、それまでに張られた糸を回収するかのようでした。
人の存在は何なのか?
自分を解ってくれる、愛してくれる存在があって成り立っている、自分が今ここに存在するのは自分だけが決められるものではないのではないか?
それに抗うけれど抗えない、でも足掻く、そんなラストでした。
静かな部屋の一室で、ほぼその空間だけで、最後までたった一人です。
静粛な中、時にユーモラスな、時に上辺だけから琴線に触れる会話が続き、そこから一転してあの大胆で堂々な舞台になります。圧巻でした。
【いもたつLife】

作・演出・出演 サウサン・ブーハーレドさんはレバノン人です。その彼女が作・演出・出演の劇を、あまりにも国内情勢が異なる日本人の私が読み解くことはできないことを前提において鑑賞しました。
内容は、サウサン・ブーハーレドさんが体験したごく普通の日常や恐怖の日常やそこから得た死生観を表現したものです。
舞台はベッドだけ。その上だけで悪夢を再現します。再現は抽象的な彼女の夢の表現です。
ユーモラスなはじまりですが、すぐに訳がわからないことが始まります。
三つ目の足が出てきたり、もちろん幻影です。その後も胎児や化け猫が現れたりというホラー映画のような舞台、その後は彼女自身が妖怪のように、まるでカフカの変身のようにもなります。
それらはすべて暗がりのベットの上でいつの間にか現れては消えです。
でも最後は癒しに映像も流れます。
レバノンで何が起こっているかをこちらに訴えるのでは決してありません。
彼女が体感していることを彼女自身の身近な存在で表現します。(猫も家にいた猫、そして祖母が亡くなったことからこの劇の創作が始まったそうです)
ですから、誰もが作れる劇ですが、私との決定的な違いは、“自分の抱えているものをどうしても訴えたいか”であると感じました。
あまりにも恵まれているのでしょう。
レバノンでというよりも、現在世界の多くの紛争や飢餓の地域で何が起きているかにあまりにも鈍感であることを痛感する観劇になりました。
【いもたつLife】

SPAC新作の意欲作です。
因幡の白兎とそっくりの神話が、北米・南米大陸に数多く残っている。しかし、米大陸の神話は、主人公が河を渡り神に会いに行き、そこから求婚があるという一連の神話だが、日本は、河を渡るのは因幡の白兎で、求婚は別の神話になっている。何故か?
それは、“アジアでそれらの元になる神話があり、それがまず日本に伝わり、そのあと北米に伝わったのではないか?”“伝わるのに時差があり、日本ではバラバラに、米大陸ではそのままで伝わり残ったのではないか?”というクロード・レヴィ=ストロースの仮説を、SPACの演劇としたのが、「イナバとナバホの白兎」です。
神話を想像し、具現化しています。
まず因幡の白兎が第一幕、次にナバホの伝説が第二幕、そして想像の神話が第三幕です。
いずれもSPACらしい演劇・演出でした。
声明を想わせるオープニングで、台詞づかいは始終それに近く、繰り返しが基本。そして、主要人物はムーバーとスピーカーに分かれるSPACの十八番です。また、音楽も和があり洋があり、和洋折衷になります。それらは打楽器と管楽器が中心でこれもSPACお得意です。
コミカルな演出が随所にあり楽しませてくれて、一方、神話に迫っていくという流れ。こちらの想像力も掻き立てる演劇です。
父との葛藤は普遍のテーマであることを匂わせていました。
もう一回鑑賞を予定しています。とても楽しみです。
【いもたつLife】

南アフリカにとってアパルトヘイトが遺した負は、私達には想像できません。
この演劇は、不条理の王のユビュ王がどんな差別・支配をしていたか、その妻は黒人で夫に差別・支配される側です。不条理な仕打ちを受けています。
けれど、夫の本当の姿が、少しずつ露になるという展開です。
夫と妻のやりとりの他、犬やワニの人形が登場します。彼らがユビュ王の腹心のように王の悪事を後押しします。
そして、ユビュ王は証言台に立ちます。
人と人形のリアルな舞台の演劇以外に、スクリーンにアニメが映されたり、実際の南アフリカの映像が映されたりします。
それらはユビュ王はじめアパルトヘイトの実態を想像させます。
ユビュ王の姿が露になると何でも有りだったのか、を感じます。それと同時にアパルトヘイト撤廃から20年以上を経てもまだまだ傷があることを想像させる劇でもありました。
【いもたつLife】

シェイクスピアの「リチャード三世」を大胆な戯曲にした野田秀樹作をシンガポールのオン・ケンセンが演出、スケールが大きい国際色豊かな演劇に仕上がっていました。
出演者が凄い、イコールこの演劇の肝にもなっています。
歌舞伎、狂言、宝塚、バリの影絵、それらの要素が野田秀樹の「三代目、りちゃあど」をより多彩に多様にしています。言葉も日本語、英語、インドネシア語が乱れ飛び、音響も物静かから大音響まで、照明もモノクロームから派手で舞台を巡るようなものまで、視覚・聴覚・頭に訴えてきます。
日本の文化からインドネシアの文化までが飛び回っている舞台に圧倒されました。
とにかく役者がみんな力強くダイナミック。
そして原作の言葉遊びでのギャグも入るし、言葉の二重性も印象的でした。
主となるのは法廷で、被告はリチャード三世、戦争と跡目争いで犯した大量殺人を問うというもの。
検事が作者のシェイクスピアというのがこの戯曲の肝です。被告の弁護はシャイロックです。そしてシェイクスピアは彼の描いた人物達の逆襲を受けます。何故リチャード三世をせむしのびっこにしたのか・・・等々、それはシェイクスピアの生い立ちに問題があるという展開に。
これを軸に、劇はリチャード三世の跡目争いの歴史をたどりながら、突然現代の華道界の跡目争いをなぞったりと破天荒な舞台になります。
そして追求していくのは、今生きているのは幻想のひとつなのではないかに収斂していきます。
シェイクスピアの物語が、作者を参加させた裁判になり、そこには他の物語の登場人物も現れるという入れ子構造で、それに加えて、リチャード三世の物語と華道界の“りちゃあど”の物語が表裏になっていて、それらの表現が、歌舞伎や狂言や宝塚そしてバリの影絵と、とても複雑です。繰り返しますが台詞は3か国語とますますこんがらがりそうなところを、面白く纏めてあるという、これまでにない体験の観劇でした。
【いもたつLife】

主人公は認知症のある老人、彼が見知らぬ男に追われて荒野を彷徨う様を様々な手法で(台詞はなく)描写します。
彷徨う老人には、今抱えている問題とも思えることから、過去の想い出や辛かったことまでが幻想的に暗喩として表現されます。
表現方法は、舞台の役者であり、人形であり、影絵でありで、観客の想像力のあちこちが喚起されます。
また、舞台の役者でリアルな映像を、人形は文楽を思わせるほど緻密な表現で老人の気持ちを、影絵は大胆で老人がどんな過去を過ごしたかを、こちらに投げかけるようにしています。
認知症は極めて現実的な社会問題で、個人的にも直面している問題ですので、とても身近です。
本人は現実がわからないことをとても不安に感じているはずです。けれど一方では、これまでの人生を楽しく振り返っているのかもしれません。そんな認知症の人の立場に立って作れられていて、かつ、これからの高齢化社会で高齢者と付き合う私達の嗜みを示唆している作品でした。
追伸
5/5に、5月の「毎月お届け干し芋」出荷しました。
今月のお宝ほしいもは、“紅マサリ四切りほしいも”です。
ご興味がある方は、干し芋のタツマのトップページからどうぞ。
干し芋のタツマ
毎月お届けの「今月のお宝ほしいも」の直接ページはこちら
今月のお宝ほしいも
【いもたつLife】
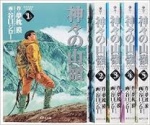
全5冊で量も質も濃い漫画ですが、一気にいきました。
舞台は1990年頃のエヴェレスト。
約70年前にイギリスの登山隊のジョージ・マロリーのカメラを偶然見つけ、初登頂したのではないかという、仮説を持った深町誠。
カトマンドゥで調査を始めると、ビカール・サンという男と接点ができます。彼は伝説で孤高の山男の羽生丈二で、カメラは羽生(ビカール・サン)が見つけたのではないかと推測、そこで羽生に興味を持ち深町は羽生を追うと、彼はとてつもない、今まで誰も成し得なかった登頂を目論んでいた。
ビカール・サン(羽生)に引き込まれるように深町もエヴェレストへ。
深町の目線で物語は進みます。彼も十分に山屋で、孤独を背負っています。
羽生という人物を調べれば調べるほど、山しかない羽生に共感していく深町。羽生は野望を遂げるか、エヴェレストの神々に嫌われるか、そこがメインです。
羽生は「エヴェレスト最難関ルートの南西壁の冬期単独、無酸素」という不可能に挑戦します。なぜ羽生はその登攀にとりつかれていて、つき動かされていて、自分の生のすべてをそれに捧げます。
その羽生を見届けるのは自分しかないと、深町もすべてを賭けます。
それを軸に、そしてマロリーのカメラの謎は?
羽生が唯一愛した岸涼子との関係は?
また、孤高の羽生が唯一心を許した山男の岸涼子の兄の文太郎は、羽生との二人の登山で命を落とします。文太郎を亡くしたことで背負った十字架、その清算がエヴェレスト制覇であること等の複数のエピソードが羽生という男が持っている、背負っているものを重厚に語ってくれます。
また、絵が見事でした。
人を寄せ付けない険しい山、そこに挑む姿、神々に受け入れられなければ=そこまで自らを山に賭けなければ、神は微笑まない、そんな描写が伝わる絵です。
この漫画と対峙している間中、羽生は矢吹丈と同じ類の人間だと強く感じていました。
決して立派だと褒められる人物ではない。泥臭く生きていくしかできない不器用な男です。
でも生きていることの密度は誰よりも濃い、そういう男です。
素晴らしい作品でした。
追伸
5/5は「立夏」でした。二十四節気更新しました。
ご興味がある方は、干し芋のタツマのトップページからどうぞ。
干し芋のタツマ
二十四節気「立夏」の直接ページはこちら
立夏
【いもたつLife】