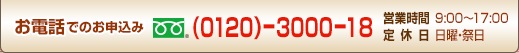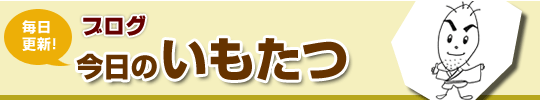いもたつLife
【SPAC演劇 ガリレオ ENDLESS TURN 多田淳之介 演出

ベルトルト・ブレヒト原作「ガリレオの生涯」は未読ですが、それを翻案した演劇でしょう。エンターテインメントとして楽しくしているだけでなく、700万年前から2045年までを追うスケールの大きさがあり、しかも上手く纏まっていて、内容は多分原作に忠実に人間の弱さ、ずるさ、宗教等に縋ってしまう性、それが社会を作り慣習になり権力や貧富の差を生み、良くも悪くも諍いが絶えないことを謳っています。またAIも参加させて作り上げているということで、だからそれを踏まえて未来への示唆も匂わせています。
とても充実の140分でした。
劇は、<エンドレス>パートと、<ブレヒト>パートに分かれています。交互に繰り広げられます。そのエンドレスパートはとにかく楽しい、そして700年前からの人類史を追うのですが、それが端的に纏まっていてしかもブレヒトパートにしっかりと後押しになっています。それだけ原作に普遍性があるのでしょう。
エンターテインメント性はミュージカル仕立てを観客に語り掛け参加を促すことが積極的に取り入れられています。中高生鑑賞上演ではかなり盛り上がるそうで、解ります。
けれど本質はガリレオの、人の、生き様です。強くも弱くも人らしく、でもガリレオは突き動かされていたことが解ります。とても人間らしいです。
素晴らしい演劇でした。
【いもたつLife】
【新国立劇場 令和8年初春歌舞伎公演】

通し狂言 鏡山旧錦絵?四幕七場(かがみやまこきょうのにしきえ)
序 幕 営中試合の場
二幕目 奥御殿草履打の場
三幕目 長局尾上部屋の場
塀外烏啼の場
元の長局尾上部屋の場
大 詰 奥庭仕返しの場
右大将頼朝花見の場
「女忠臣蔵」と言われているだけに、女形の見せ場が盛りだくさんの演目でした。
それが皆上手い。
地位は人を作る通り、庶民出身の尾上は立派な武家です。そしてそれに仕えるお初も。
この二人が内匠頭と内蔵助に重なります。そして岩藤が吉良です。
岩藤の策略が少々安易ではありますが、それが全く問題にならないほど、人間模様が演じ語られます。ですからとても歌舞伎らしい演目でした。
良かったです。
【いもたつLife】
【マリナート 松竹大歌舞伎】

地方巡業で地元開催になりました。嬉しいです。
一、泥棒と若殿(どろぼうとわかとの)
山本周五郎 作 矢田弥八 脚色 大場正昭 演出
ひょんなことから伝九郎と成信の共同生活が始まり、深い友情で結ばれます。成信は伝九郎によって魂が蘇り国を治める決意をします。伝九郎は成信との別れを惜しみますが、立場の違いを察し、泣く泣く成信を見送ります。
立ち直る二人で、人生の綾を描いているのですが、綾はきっかけです。二人とも立ち直るだけのモノをもっていたのです。でも出会わなければこうはならなかったのですから、人はどうなるか紙一重です。
うらぶれた運命を嘆きながら受け入れる潔い武士、そして国を背負う決意をする崇高な若殿 成信を中村種之助が、それを下支えする陽気で人が好い泥棒 伝九郎を中村歌昇が、その人となりを察っするような演技が見所でした。
華競芝居賑(はなくらべしばいのにぎわい)
二、お祭り(おまつり)
歌舞伎ならではの舞踊です。親子三代、一座あげての、披露も含めた楽しい演目になっていました。
地方巡業は役者も裏方も大変ですが、またぜひ来てほしいです。
【いもたつLife】
【spac演劇】ハムレット 潤色・演出 上田久美子

演出の上田さんが演出ノートや、インタビューに答えた文章でも、知や科学を突き詰めることで発展したこの社会は行き詰っていると記しています。また、シェークスピアは自然を含めたコスモスを描いているとも記しています。
そして主人公のハムレットは近代西洋主義の象徴で、オフィーリア(今回の主人公)は論理的ではない象徴であり、自然に抗う存在と、自然に還る存在の対比としている劇です。自然から観たハムレット(=現代社会)としてこの「ハムレット」を演出してということです。劇後のアフタートークでもそれを強調していましたし、その時のゲストの河合祥一郎さんもその視点の上田ハムレットを絶賛していました。
話は変わりますが、チンギス・ハーンは都市だけで生活していることに遊牧民として警戒していました。都市を造って生活したフビライ・ハーンもその精神を持っていたと言われています。
このハムレットは、自然を征服したとしている現代を警戒しているのではなく、それが通じないと言っています。また、自然の畏敬を合わせています。
でも実際の劇はとても楽しいものでした。話はハムレットで、そのセリフもふんだんに入れ込まれていますが、笑いが溢れます。時折、辛辣に人は死ぬと屍になる実際を見せたり、魂とは、どこに行くのかも問いますが。
今回も自分は何で自分なんだろう、社会の恩恵を受けながら、それに従っているだけか、その恩恵とは何かをも考えていきたくもなりました。
【いもたつLife】
【2025年11月 グランシップ文楽】

昼の部、夜の部共に、今までにない盛況ぶりでした。
【昼の部】「義経千本桜」~道行初音旅
歌舞伎の舞踊もよいですが、文楽の舞踊も艶やかです。そして人物の心情がこうも伝わるものかという動きです。
コミカルな狐がアクセントになっているのも歌舞伎と通じます。
【昼の部】「新版歌祭文」~野崎村の段
文楽での世話物を鑑賞すると、喜怒哀楽が表現できることがよく解ります。
どうしてもダメ男の題材が多くなるのですが、この劇の久松もです。でも男が弱いというよりも人が堕ちていくのは、ほんの少しの考えの甘さというのはいつの世もです。
それを憐れと、救いの手を伸ばすことが仇になることも常で、ここも人の弱さからです。わが子を谷底に落とす覚悟はできないものです。
それは置いておいて、この劇も一人一人の心情表現に見入ります。
立場立場で変わる人の態度も含めてです。
最終版はかなりユーモアが含まれますが、解説本のその後をみると虚しさを覚えます。
【夕の部】近松門左衛門没後三百年「曾根崎心中」~生玉社前の段~天満屋の段~天神森の段
九平次の罠に掛かり、理不尽にも破滅する徳兵衛に追い打ちをかける九平次の悪口雑言から、お初と徳兵衛が心中を決めていく、成してしまう、見所の多い文楽で、天満屋での縁側にお初、その下に徳兵衛という有名なシーン、天満屋を出ていくときの火打石というシーンももちろんですが、今回は最終の天神森の演出に唸りました。
静寂な闇の中で二人は天神森に向かいます。そして心中は決めているけれど徳兵衛はお初を刺すことに逡巡します。けれど二人はあの世にいくことこそが、添い遂げることが、清く、そして救いになり、そして何よりも二人の愛が成就することを信じ願っていて、これしかないのです。
この重厚な段を、人形の表現はもちろん見事ですが、それに合わせるのが、三人の太夫と、三棹の三味線です。
静かに語る声も音も三つになることで、様々になります。静寂とお初と徳兵衛の心を、たくさんの音色や強弱で仕草に合わせてそれを観るものに目だけでなく耳に心に訴えかけていきます。
見事でした。
【いもたつLife】
【2025年11月 大歌舞伎】

「御摂勧進帳 加賀国安宅の関の場」
前半は厳かな、弁慶が義経を撃ち打擲するお馴染みの勧進帳が、後半は弁慶大活躍の巻になります。これがユーモアたっぷりコントのようですが、歌舞伎の様式をしっかりと踏まえています。
「鳥獣戯画絵巻」でも感じましたが、歌舞伎は柔軟にされます。自由度が高い、だけど根底には歌舞伎の世界を崩さない、落語とも似ています。
「道行雪故郷 新口村」
あの世で添い遂げる愛、心中するしかない切ない清元舞踊です。この手の話は映画でも様々に演出されますが、清元の語りと演奏が入ると舞台美術と相まってせまってきます。今でも誰でもこうならないように生きているのだけれど、陥ってしまうことを感じてしまいます。
「鳥獣戯画絵巻」
役者が様々な鳥獣に扮しての舞踊ですが、三味線、和太鼓だけでなく打楽器の演奏が加わります。
ここも捕らわれない自由度が高いことを示します。そしてコミカルで、同じ舞踊でも「道行雪故郷」とは全く違う演目です。
「曽我綉侠御所染 御所五郎蔵」
侠客の五郎蔵の粋な序盤を見ているだけに、本編に入った五郎蔵の最後は悲しいです。格好良いをはき違えています。五郎蔵という人物像で何を見せたいのかを考えます。
日常に思いがけないことが起きるとどうなるのか、を見せられているのでしょう。
いつもは粋で格好良い姿を通す五郎蔵は、とんでもない奴で終わらなければならなくなる。歯車が狂うと、それも自らで狂わせてしまうと情状酌量もありません。
下手に腕に覚えがあると、下手に粋を通そうとすると、それが粋ではないのに解らない。
怖い話です。
劇自体はとても好きな見ごたえある歌舞伎で、後味は悪いですが、それも世の中らしく面白かったです。
【いもたつLife】
大長編 タローマン 万博大爆発 2025日 藤井亮

子供の頃見ていたウルトラマンはじめの特撮の匂いがプンプンします。そして中身は悪ガキ。地球侵略の奇獣を上回ってタローマンのでたらめは、自分のガキの頃の分身のようです。
そして最後はタローマンのそろい踏みというサービスです。
このバックになるのが岡本太郎の哲学と芸術だから拍手です。
【いもたつLife】
【spac演劇】弱法師 石神夏希 演出

三島由紀夫が翻案した能の演目「弱法師」を原作を、spacが解釈した劇です。
戦災で盲目になり両親と離れてしまい物乞いをしていた5歳の俊徳は、川島夫妻に拾われて何不自由なく育てられます。15年後、産みの親の高安夫妻が現れ、家庭裁判所で調停が行われるという設定です。
俊徳は王様のようにふるまいます。それに対して奴隷のように従う川島夫妻、怪訝そうだった高安夫妻は俊徳に気に入られるために、同じように俊徳の言葉の奴隷になります。
調停役の級子だけはこのやりとりを冷静に見つめます。
台詞は三島由紀夫にみえていた世界でしょうけれど、今の社会にも通じます。でも今の社会は当時よりも見えにくくされていて、三島(俊徳)の声を用心深く今の情勢に置き換える作業をすると、ぞっとする社会の病を感じます。
それは置いておいて、劇はそんなやりとりを二度繰り返します。
その中で注目は、俊徳は華奢で若い女性、級子は大柄で威圧的な男性だったのが、二度目は逆になります。対照的な役者が入れ替わるのです。
一度目の怖さが増幅されます。同時に、俊徳の心の空虚や迷いがその深刻さが増します。そして級子の役割、論理的な傍観者であり病んでいるモノと対峙しなくてはならない社会で不可欠な役割の重要さもひしひしと伝わってきます。
この劇は俊徳の魂は救済されるか、どこに行くのかを問う、死を考る中で避けて通れない、でもあまり考えたくないテーマを投げかけていると解説がありました。確かにその通りですが、その迷ってしまう魂は、三島由紀夫ならば戦争体験と、安保闘争が背景にあったように、そこから時代を進めた現在の混迷、繰り返しますが、本当は一触即発で戦争が起こってもおかしくないのに、社会の側は問題ないと取り繕って、解りにくくいている現代の情勢が、実は私たちを不安にさせていて、それを問題提起しているということが込められていると非常に感じる観劇でした。
【いもたつLife】
【グランシップ静岡能 能入門公演】

敷居が高い、解らない、とこれまで遠巻きにしていた能ですが、この公演で払しょくされました。
歌舞伎と能の違いは300年の時代の差から、歌舞伎の江戸時代と、その前の中世に生まれた能という、この解説は端的で素晴らしい。それは浮き世と憂き世の差です。
死生観が強く打ち出されているのが能とのことです。
プログラムも良かったです。
「第一部」 は謡いですが、稽古をしている小学生から大学生までのお披露目で、次はもちろん能楽師の登場です。そして最後は観客を巻き込んでの謡の稽古の触りでした。
「第二部」 は演目「熊坂」ですが、その前解説は演目に対することだけでなく、前述の能の時代背景のことや、能面の狭い視野を通しての能の静と動、身体能力から精神を鍛える、養うのが本文の能の精神を、お仕着せがましくなく、少しユーモラスに解説してくれます。
こうなったら「熊坂」が楽しみです。
「熊坂」は優しい演目ということも相まって十分に楽しめました。
【いもたつLife】
【大歌舞伎 八月納涼歌舞伎】

一、 男達ばやり(おとこだてばやり)
粋な江戸っ子を茶化している喜劇です。
口に出したことは何があっても、命をかけても意地を通そうとします。それが面白いし、江戸という時代が懐かしくもなります。
この演目は大正15年初演の新歌舞伎で、きな臭い時代だったからこそ、このような喜劇が生まれたのでしょう。
二、 猩々(しょうじょう)/団子売(だんごうり)
二つの舞踊を、幸四郎、勘九郎の二人が続けざまにみせてくれます。
猩々は酒飲みの舞、そして尽きない酒壺酒が好きなら自分を見ます。
団子売は夫婦の舞、こちらも息が合っています。
堪能しました。
【いもたつLife】