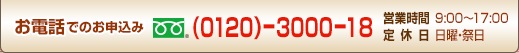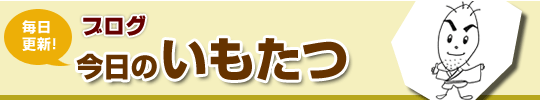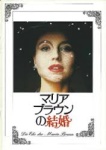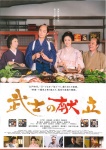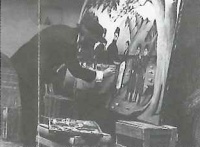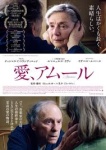銀幕倶楽部の落ちこぼれ
ローラ 1981西独 ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー

マリア・ブラウンの結婚の後を受け継ぐ、その後の西ドイツの姿の映画でした。
復興が軌道に乗った後に起こる、賄賂、癒着、権力の腐敗、私利私欲化、それらを背景に、
中年男と美しい娼婦の愛の物語ですが、皮肉たっぷりの内容です。
表面的には純愛物語です。
州の役人、建設局長として赴任した堅物男が、街で会ったローラに恋します。
娼婦とは知りません。
どうしてもローラに会いたい局長を見ていた部下は、
局長をローラが要るクラブ(売春バー)に連れて行きます。
唖然とした局長、なにしろまじめ一筋でしたから。
でも局長は気を取り直して、ローラをモノにする、というお話です。
純愛は表面だけ、一皮むけば欲望だらけの物語です。
ローラは、街一番の建設会社の社長の愛人です。
その社長は賄賂で会社を大きくしました。
新しい局長ももちろんもてなします。
局長はローラが娼婦を知るまでは、局長として穏やかでした。
公共事業はこれまで通りで構わないというスタンスです。
それが、ローラが建設会社の社長の愛人と知るや、手のひらを返します。
これまでの不正を暴く、全うな役人に、鬼のようになります。(正義です)
困ったのは社長をはじめ、市長達、みんな恩恵に預かってましたから、
そして局長がやっていることは、グーの音もでない正義です。
そこにローラが一役買って、局長と彼らの橋渡しです。
もちろん、局長はローラに丸めこめられますが、ローラと結婚という、
純情男いとってこれ以上ない果実です。
彼らも安泰、そして一番貰いが大きかったのがローラです。
一介の娼婦が大金持ちの仲間入り、しかも一目置かれる存在に、
しかもかねてから欲していた自分が属するクラブも、愛人だった社長に買ってもらい、
しかも、まだ愛人関係を続けるというしたたかさです。
正義が完全に駆逐されるという、根も葉もない解決です。
でも表面的には純愛です。
ローラは局長に正体が知られた時には、心から嘆いていましたし、
彼と居る時はかれと同じく純情でしたから。
でもそれとこれとは違うのが現実だったということです。
映画中他にも人に嫌な部分を映しています。
金持ちが貧乏を嫌うところ、東から来た(東ドイツ?)からきた女性を馬鹿にするところ、
いかにも役所の人々を映すところ、金持ちの社長を取り締まらない警察官、
街の建設計画が無事に遂行されることになった時のシーンも見たくない映像です。
この映画も監督にとって、自国を憂い愛するものだったことが伝わってきます。
【銀幕倶楽部の落ちこぼれ】
マリア・ブラウンの結婚 1979西独 ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー
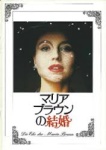
戦後の西ドイツの復興と合わせて、一人の女(一組の夫婦)の半生です。
日本の復興と心情的に重なると個人的には感じるので、
よその国の出来事ではないと、登場人物に感情移入します。
主人公はマリア・ブラウン、わずか半日と一晩の結婚生活だけで、
夫は戦地に行きます。
終戦を迎え戦死したはずの夫が生還しますが、
マリアはその時には米軍兵士の愛人になり、子供まで身籠っていました。
思わず米軍兵士を殺害したマリアですが、夫が罪をかぶり投獄生活に。
その間マリアは経済的に成功し、夫を迎え入れますが、
夫は妻に厄介になることを避けてカナダに。
数年後、夫も経済的に成功しよりを戻しますが、悲劇が訪れます。
マリアは年月とともにしたたかになっていきます。
その様子と西ドイツの経済が豊かになっていく様が織り込まれます。
マリアはアメリカ人にもフランス人にも体は許しますが、
心はドイツ人の夫に捧げています。これも西ドイツの姿を描いています。
マリアが貧困から抜け出す姿が主に語られいるのですが、
彼女の母や親友とその夫が問題を起こしては、
彼女を苦悩させます。
これも戦後の西ドイツ自体の苦悩です。
ライナー・ヴェルナー・ファスビンダーは、
祖国のあの苦しい10年間(1945年から1954年)を憂いて、
愛してこの映画を撮っています。
もう一度鑑賞してもっと深くドイツの歴史とその場を汲み取りたくなった作品でした。
ラストシーンは、西ドイツがワールドカップ初優勝のラジオ中継が、
マリアと夫の運命を示唆しながらリンクします。
栄光を手にした瞬間、国民が狂喜乱舞した瞬間に、
マリアの悲劇を重ねます。
監督はとっては真に西ドイツが喜べる瞬間ではなかったのです。
非常に濃いメッセージがある名シーンです。
【銀幕倶楽部の落ちこぼれ】
武士の献立 2013日 朝原雄三
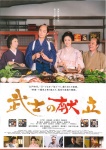
正の循環の物語です。
恵まれた環境、そして、自分を鍛える心がけを身につけた者、
それが主人公の夫です。
主人公は、12歳で天涯孤独になりました。
でも彼女には世の中を渡れるべく、
亡き母から授かった超一流の料理の腕がありました。
彼女(主人公)は、その才能と努力で得た料理の腕を
利己ではなく利他に活かすことが身についていました。
母代わりの愛も受けていたからです。
主人公は12歳までの実母の愛と、
12歳からの母代わりの愛を受けていて、
それを開花させる機会を得ました。
この映画は、その部分を見せる映画です。
主人公の夫は、藩に奉公を信条とする由緒正しい武家の次男坊です。
家は包丁侍といわれる、一見武士の本道からは外れる家系です。
夫はそこに引っかかりを持っていました。
(これにまつわる自己評価の決めつけがあり、それがこの物語を進展させます)
『滅私』が武士に必要不可欠の時代、
若き夫はそれに従うことを良しとしません。
大体が武士は戦う者という幻想を背負っています。
若気の至りであってもそれを続けることは、
妻(主人公)にとっても、家(両親)にとっても、
『人でなし』となる行為です
でもそれには気がつかない、
だから妻が身を捨てて夫に抗します。
その姿は、不幸から転換できた彼女の信条がそのまま現れた姿です。
時は和平と成った江戸時代です。
でも常に水面下では争いはあります。
これも世の常です。
だから若き夫は、
環境に踊らされてしまいます。
派手なモノに本質を見出せなくなっってしまうのです。
家の生業の包丁侍の価値を見出せないのです。
それに目覚めさせたのが主人公です。
不幸に落ちかけた彼女は、
幸運にも出会った母代わりに救われました。
でも彼女にはそれを受け入れる資質もあったのです。
その恩返しのように彼女は夫に尽くしました。
わがままな塊の夫も、ついに妻の想いにしたたか参るかのように、
彼女の無垢の気持ちを受け入れる覚悟を持ちます。
そういう物語でした。
世知辛い世の中でも正の循環は機能する。
それを声高に示していました。
ちょっと違う視点の一言、
江戸を再現したセットもロケも良かったです。
物語の背景であり、物語の影の主役の料理もリアリティあり、
そして、主人公はじめ登場人物(特に女性)の衣装も
とても良かったです。
【銀幕倶楽部の落ちこぼれ】
ピロスマニ 1969グルジア ゲオルギー・シェンゲラーヤ
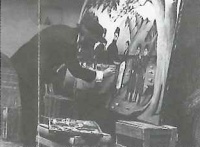
生前認められることなく貧しい生活のまま亡くなった画家の半生です。
ピロスマニの時々の精神的や経済的な苦悩とともに、彼の絵画が写されます。
観客は彼がどんな心境で数々の絵を仕上げていったのかを探ることになります。
絵を描くこと以外は不器用な主人公は、絵が認められなければ、困窮するしかありません。
認められない中で描く絵は、
自分を信じるから描き続けられるのか、食い扶持の方法が絵だったのかは解りません。
確かなのは真剣だったことで、紛れもないことです。
映画は一切の説明は排除しています。
台詞やシーンも彼の人となりを知らせるのにとどめます。
救われるべき英雄だったとすることもなく、
ことさら悲劇的に撮ることも控えていて、
報われなくても絵を描くしかないピロスマニの日常を伝えます。
多分、推測できる現実を再現したかったからでしょう。
それは一人の芸術家の儚い一生です。
でも賭けるものがある男の生きる美しさが伝わります。
一芸に取り憑かれた者の濃厚な人生の満足も感じます。
人は今生きている生き方しかできない、それは天才も秀才も凡人も同じかもしれません。
追伸
12/7は「大雪」です。二十四節気更新しました。
ご興味がある方は、干し芋のタツマのトップページからどうぞ。
干し芋のタツマ
二十四節気「大雪」の直接ページはこちら
大雪
【銀幕倶楽部の落ちこぼれ】
偽りなき者 2012丁 トマス・ヴィンターベア

人は感情で結論を出しておいて、理屈を付けてもっともらしくします。
最初から答えを準備しているのだから議論の余地なんてありません。
それが意識的ではないことがほとんどだから、話は厄介です。
そして、一度魔女狩りが起こると、それに加担することで正義の味方気分を味わいます。
この映画を含めて『完全な冤罪』の映画を観ると、
被害者になってしまう可能性はいつでもあり、その不安と、社会の脆弱さを感じ、
この映画では、実際に駆られてしまう恐怖に追い詰められてしまう錯覚まで起こります。
デンマークの田舎町、街の人々は皆が協力して生きています。
主人公のルーカスも幼稚園に勤めながら、街の同年代の男達とは家族ぐるみの付き合いを何十年も続けています。
仲間と一緒に飲み、遊び、仲間の子供達の父親・兄貴代わりとして、街に尽くす男、必要な男で、その中で生きがいも感じていました。
もしあの事件が起きなければ、離婚はしているものの、不幸な人生なんて他人事だったでしょう。
その事件とは、幼稚園の幼女クララ(ルーカスの親友テオの娘)の些細な嘘ではじまりました。
「ルーカスのおちんちんが立っていた」
ルーカスが大好きなクララの、ルーカスの気を引きたいがために出た言葉でした。この直前にクララの兄(中学生か高校生)からIpadの卑猥な映像を見せられて、「立っている」という言葉を植えつけられていただけでした。悪いシチュエーションは重なります。園長先生がそれを聞きつけたのです。
園長はこの時点で保身からか、ルーカスを変質者(犯罪者)に決め付けます。それを裏付けるために、教育委員のような男に相談します。男は園長と同じです。最初から決めています。だから、クララを誘導尋問にします。
(人は自分が安全地帯にいることができれば、日常でないことが起こって欲しいと望んでいる悪魔の顔があるのでしょう)
もちろん、犯罪を未然に防ぐことは大事です。可能性は極力排除する努力は必要ですが、自分の行為により何が起きていくのかを何も考えなさすぎです。
本当に、感性がないというか、安易なことをするのが人です。
実際に園長と男の安直な行為は、ルーカスの人生と家族を滅茶苦茶にし、クララの心に深い傷を負わせ、幼児を持つ家族に不安を与え、街中の人々に魔女狩りさせる怒りを植え付けました。
ひどい仕打ちが続き、ルーカスはぼろぼろになりますが、それでも心を折ることなく、街で暮らします。
街の人達(特にテオ)はその姿に、嘘をついているのはクララではないかと思い始めます。
そこから物語りは好転します。
そして1年の空白がありラストのシークエンスです。
その1年後は、ルーカスの息子の猟解禁日です。(成人式みたいな感じ)
ルーカスの疑惑も晴れて和やかに式典が進みます。そして明朝ルーカスは息子と初の狩りに出かけます。他の友人達も参加すています。
その狩りをしている最中に突然、
至近距離から“ルーカスが撃たれます”未遂ですみましたが。
(この前振りがあります。ルーカスの飼い犬が殺されるシークエンスがあります)
これで映画は終わりです。
一度魔女のレッテルを貼られた男は、その十字架を一生背負うのです。
この物語には悪人はでてきません。(強いて上げれば園長と男です。彼らは権力を持っていることに無自覚で、それは大罪です)
気が良い街の住民は魔女がいると魔女に対して鬼になるのです。
戦慄の映画でした。
(魔女にされてもルーカスを信じ、支援する者達もいました。冷静な判断ができる人達でした。これも現実です)
追伸
12/6に、12月の「毎月お届け干し芋」出荷しました。
今月のお宝ほしいもは、“有機安納芋のほしいも”です。
ご興味がある方は、干し芋のタツマのトップページからどうぞ。
干し芋のタツマ
毎月お届けの「今月のお宝ほしいも」の直接ページはこちら
今月のお宝ほしいも
【銀幕倶楽部の落ちこぼれ】
愛、アムール 2012仏/独/墺 ミヒャエル・ハネケ
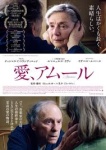
ミヒャエル・ハネケ作品の中でも、一番観客に委ねています。
高齢社会での嗜みを踏まえたうえで、
『愛』と『尊厳』と『命』に対しての考察を真剣に促していて、
答えではなく、向き合うことを提示しています。
物語の主人公はフランスの中産階級、音楽家として成功した人生を送った老夫婦です。
少ない余生を二人で充実した時間を共有していましたが、
ある時、妻が病気になり、夫が看護する生活に変わります。
妻は気丈な女性であることがエピソードで語られます。
体や精神が病んで生きながらえることは、彼女にとって死よりも辛いことです。
病院には行かない約束を夫と取り付けます。
夫は妻のことを“わかっている”のですが、死を引き伸ばしたい想いと、
妻が生きたい生かし方で死を早めることの、狭間に最後まで苦悩します。
妻は壊れていく姿を誰にも見せたくはありません。
近隣の住民はもちろん、介護士も医者にも、そして娘すらにも。
そして夫にも見せたくないことを夫は知り尽くしています。
けれど妻はすでに一人では生きることも死ぬことも出来なくなります。
そして、夫は二人の最期を決めます。
ラストシーンは老夫婦の娘ががらんどうになった両親の住まいにひとり佇むシーンです。
彼女は子供の頃両親の愛のささやきが漏れる声で幸せを感じていたというシーンがありますが、
その余韻を感じているかのようです。
娘役は、イザベル・ユペールです。彼女だけは結末を誰よりも心で受け入れているように見えます。(個人的には、イザベル・ユペールだからそれを感じさせて、これも意図的でしょう。「ピアニスト」をかぶるからですが)
夫の行為に対して、倫理的に、法と照らし合わせて、ということを持ち出すのは野暮です。
それを超えた考察の提示をしている作品だからです。
だいたいが人が決めたものなんて最大公約数でしかありません。
豊かで長生き、でも世知辛い、皆忙しい、現代の社会で夫婦が寄り添う時間は体の自由が利かなくなる直前に訪れるものかもしれません。
(昔は寄り添う時間が稀だったかもしれません)
その時点で、二人の心が惹きあえるとしたら、それほど崇高なことはありません。
そして、外野はとやかくいう権利はないのです。
物語中も、娘が意見するシーンがありますが、それに対して夫(父)は毅然な態度をとります。
老夫婦は二人で二人の最期を決めたのです。
後悔が『ゼロ』の行動ではなく、後悔よりも優先するものがあったからです。
それは最後の鳩のシーンと、二人が二人の城から出て行くシーンの私の解釈ですが。
だから、この映画は『愛』の物語であし、『希望』を提示していると確信しています。
【銀幕倶楽部の落ちこぼれ】
処女の泉 1960瑞 イングマール・ベルイマン

人が持つ罪を時に穏やかに、時に激しく描いている作品です。
舞台は中世のスウェーデンの豪農一家です。厳しい自然の中で食べるのがやっとというのが大勢の頃です。そしてキリスト教、神を信じることが生きる術の時代ですし、重要なテーマでもあります。
豪農の夫婦(テーレとメレータ)は敬虔なクリスチャンです。特に父テーレは自らの財産を教会のため、世のため人のために尽くすことを厭わない人格的にも立派な男です。
もちろん一族皆信心深いのですが、召使のインゲリ(父なし子を宿している女)は反発しています。
夫婦には一人娘カーリンがいます。金持ちの一人娘ですから甘やかされています。また、純真無垢の穢れなき存在です。(インゲリとは対象的な)
他にも女の召使がもう一人と、テーレの仕事を担う下僕達が3人います。皆、食べるのも大変な時代(社会)の中でも、暖をとれること、飢える不安がないことはテーレのお陰だという気持ちを持っています。
ある日、カーリンが遠く離れたところにある教会に、おめかししてローソクの寄進に行くことになりました。インゲリを連れて。途中インゲリはカーリンを一人で行かせます。(オーディンという神にカーリンを葬ることをインゲリが依頼するという暗喩が含まれています)
その後事件が起こります。ヤギ飼いの男3人(子供が一人)がカーリンを襲います。凌辱し、撲殺します。(子供は見ているだけ)そして、後を追いかけたインゲリも見ているだけです。
3人はカーリンの身包みを剥いで立ち去ります。そして夜、テーレの家にたどり着き一宿一飯の世話になります。そしてあろうことかメレータにカーリンの服を売ろうとしたのです。
血のついたドレスはすべてを物語っていました。
テーレは復讐します。3人を葬ったのです。
キリスト教の七つの大罪「傲慢」「嫉妬」「憤怒」「怠惰」「強欲」「暴食」「色欲」を登場人物に背負わせている物語です。
罪深い存在は、カーリンに手を下した3人のうちの2人とテーレですが、他にも罪を持つ者がいます。
オーディンにカーリンを葬ることを頼んだから男たちが手を下した、と後悔するインゲリ、「嫉妬」です。また同じくメレータも「嫉妬」の告白をします。テーレとカーリンの仲があまりにも良いことに対して嫉妬を抱いていたことを。
テーレも3人のうちの罪のない子供まで手を掛けています。「傲慢」と「憤怒」(怒りに任せて罪のない少年まで手をかけました。鬱憤が溜まっていたとしたら何のための信仰でしょうか)です。
しかもラストにカーリンが撲殺された場所に教会を立てることを神に誓います。それで赦しを得ようとします。なんという「傲慢」でしょう。
そしてもちろん3人のうちの2人の男は、「色欲」「強欲」「暴食」「怠惰」です。それも半端無い獣です。
殺されたカーリンと子供はどんな罪があったのかは解りませんが、殺される罪はありません。
インゲリとメレータも救われない罪を犯してはいません。
罪深い男2人は、テーレにかかり身をもって贖罪となったのでしょうか?
テーレも教会建設で贖罪ができることはあり得ません。
しかし泉が湧きました。その聖水で禊をするシーンもありました。
しかしイングマール・ベルイマン監督は、罪が償えるとは言っていません。
深読みかもしれませんが、泉はカーリンに対しての涙、ただそれだけのような気がします。
【銀幕倶楽部の落ちこぼれ】
野いちご 1976瑞 イングマール・ベルイマン

死までの時間が短いことを悟っている老紳士の一日で、
彼の生きた姿とそれを受け止める彼の姿を追った作品です。
その日老紳士は、50年間の医師としての貢献を国から称えられるという晴れの日でした。
飛行機で行くはずの旅が、クルマに変わります。
同乗者は息子の嫁と、旅の途中で出会う、その日限りの人々です。
その車中での嫁や出会った娘とのやりとりと、
旅の途中の主人公の思い出の場所に降りたつ感慨と、
それらに纏わる回想で、決して幸せばかりではなかった主人公の一生が、
主人公自身で収斂されます。
けじめがつけられるのです。
その始まりは、明け方の悪夢からでした。
主人公は、気味が悪い状況下で己の遺体と出会う夢をみます。
こういう夢や白日夢はその後も挿入されます。
愛していた婚約者が弟のものにされるリアルな情景、
その恋人は若いままに老いた彼と出会い、老いた現実を突きつけられるシーン、
すでに亡くなっている妻の若い時の不倫のシーン、
医師として失格の烙印を捺されるシーン等々。
そしてこの旅では、現実世界でも人付き合いを避けてきた、
親しい者すらもおざなりにしてきたツケが襲い掛かります。
嫁に詰問されることと、嫁と息子の不仲の実態を知らされ、さらに、
今の息子は老いた自分と同じように、
生きることに意義を見出せないでいる心境であることを嫁から突きつけられます。
しかもそれは自分と息子との関係で出来てしまったと息子が吐露していることも。
それらとは逆に、この日限りの同乗者はこれまでの彼を称えます。
彼にとっては、国から称えられることよりも喜ばしい体験です。
たとえそれが、合ったばかりの人たちが相手だから良い面しか見せないという事実であっても、その姿も彼そのものです。
親しい仲でも同様に振舞っていたはずです。
旅では彼の生き様の中でも、彼の潜在意識に深く刻まれていた出来事を映します。
長かった人生でも深く刻まれたことはほんの一瞬のことで、
いくつかの出来事が、人生を左右しているということを示唆します。
もちろんその出来事は、それが発動するまでの、
彼の行為(彼と相手とのやりとり)の膨大な時間も含めた積み重ねの結果です。
そして人間とは、起きたことで今まで生きた人生を、
今の彼は負の遺産としてだけ回想していきます。
けれど、それが徐々に変化します。
負の遺産は、彼の正があるから起きたことは見逃せませんし、
正とはなかなか認識できませんが、
まじめに生きてきたからには負だけのはずがあるわけありません。
主人公の場合は敢えて人を避けてきました。
たとえそれでも良くないことだけであるわけないのです。
主人公は、社会的に申し分ない評価を得ています。
裏腹に家庭はそれほど上手くいきませんでした。
しかもここは大事で、欲しいものを主張して手に入れていたとも思えません。
それがもどかしくて、親しい人たち(恋人、妻、息子)と彼に溝ができたように見えますし、
夢も回想もそんなことばかりが繰り返されていました。
けれど、それが徐々に変化したのです。
78歳の人生には多くのことが起きました。
生きる時間がわずかになると、絶望感に支配されます。
けれど彼は、絶望感の裏にある功績を自己が認め、もちろん失敗も受け止めて、
人としてのこれまでのすべてを統合しようとしました。
(全部があって今がある、今感じているのは全部ではない)
主人公は私達の分身です。
老いてないとしたら将来の分身です。
主人公の行為は、死を強く意識した人間だからできる崇高な行為です。
その姿を赤裸々に追った作品です。
死を迎えるのは避けられない事実です。
それに向かう意気込みとして、勇気を与える姿を目の前に提示してくれた映画でした。
【銀幕倶楽部の落ちこぼれ】
悪の法則 2013米 リドリー・スコット

リドリー・スコット監督の人生観が詰まった映画でした。
有能な弁護士が主人公です。
素直で綺麗な彼女と結婚できるという人生の絶頂期です。
彼女のためにもということで、カネ目的に、魔がさして裏社会に手を染めます。
それが運のつきで、彼女ともども破滅を迎えます。
物語はこれだけで簡単ですが、演出が凝っています。
サスペンスタッチで恐怖感も盛り上げるのですが、
登場人物を通して人生観、死生観が語られます。
それをどう感じるかがこの映画の評価のポイントです。
人生は不可逆であり、
ちょっとした心の隙、これくらいならという甘さが、
取り返しがつかないことに転がっていくという教訓も含めて、
人は“生もの”であることと、人生の綾、怖さを嫌ってほど
リドリー・スコットらしく、味わわせてくれる映画でした。
【銀幕倶楽部の落ちこぼれ】
さらば友よ 1968仏 ジャン・エルマン

アラン・ドロンとチャールズ・ブロンソンの友情映画で、
エッセンスとして二人が追い込まれるサスペンス、
濡れ衣を着せられて・・・どうなるか。が加えられています。
前半は終盤に向けての準備で、
中盤の二人が地下室の金庫破りをするところで、
二人の友情と物語の要素をすべてそろえて、
終盤の盛り上がりに向かいます。
そして二人ともカッコイイで完結です。
アラン・ドロンの各シーン、チャールズ・ブロンソンの各シーンが味わい深いです。
アラン・ドロンはモテテでもクール、ヒロインを抱き上げるシーンなんかは、
彼のファンにはたまらなかったでしょう。
チャールズ・ブロンソンの満たされたグラスにコインを入れるシーンや、
女衒のようなことをやるシーン等も見応えがある演出です。
公開当時10代、20代だったら、二人のマネをしていたかな。
なんて想像してしまう位、カッコよかったです。
【銀幕倶楽部の落ちこぼれ】