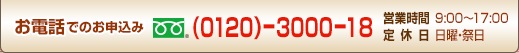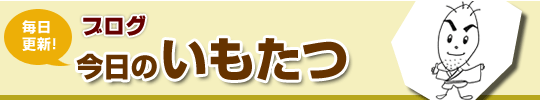- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
アデル、ブルーは熱い色 2013仏 アブデラティフ・ケシシュ

大人になれない人々(私)への警告と、大人になろうとする気概を認めてくれている映画でした。
アデルとエマの同性愛者が愛し愛され、でも破局してしまうメロドラマの形式を通して、自律しようと努力して自立するエマと、エマから自律を促されても自律できない、大人になれない(なろうとしない)アデルを対比して、自己責任である人生の行く先を考えさせます。
エマを一途に愛するアデルは、エマと愛し合うことを終着点としてしまいました。そんなことはエマにとってはありえないことです。
寂しいからという尤もらしい理由で浮気してしまったアデルは、自分が取り返しが付かない行為をしている自覚すらありませんでした。
アデルは人生の行方は偶然だと思うようにしています。けれどエマは「人生は必然」であると考えていて、それを踏まえて自己責任で生きています。
この違いは二人が暮らす環境がもたらしたことでもあります。けれど、自分で人生を開くとしたら、それを踏まえて乗り切らなければならないのに、アデルはエマからどんなに促されてもそれがわかる事はありませんでした。
破局を迎えて、でもエマに縋りつくしかアデルにはできなくて、でもエマからよりを戻すことはできないと引導を渡されて、ようやく必然の人生を生きる決心をしました。
この映画は、アデルの日常をドキュメンタリーのように映します。彼女の心理がどんな状態かをどんな意図があるのかを示すシーンではカメラは省略をしないようにしています。
二人が愛し合う濃厚なシーンだけでなく、無邪気なアデルの食べる、寝る、夢見るシーン、高校時代の友人と議論、喧嘩のシーン、教師になってから彼女が世間で振舞うシーン、すべて彼女の意図を匂わせています。
そして、エマと彼女との境遇の違いも、食べる、寝る、議論(パーティー)の描写で語ります。
生まれた階級差から始まる、同性愛に対しての考え方をはじめ、自律的な生き方の考え方の二人の決定的な違いが少しずつ露になり、必然の破却を迎えます。
それを受け入れることを拒むアデル、そしてそれを乗り越えようとするアデルまでを映して映画は終わります。
アデルは私たちです。エマは私たちがああやって生きようと今はできていない生き方を思い描いている姿です。でもお茶を濁しているのが大概です。
アデルが幸せの絶頂にいけたことは偶然で、エマに受け入れられなくなったことは必然で、それは観客自身の現状の立場を示唆しています。だからそこが警告で、しかし、エマとの決別まではできたアデルを映すことで、私たちのこれからの生き方への気概を認めていると思えるラストでした。
カラス除けになっています
カラスに悪戯されてしまいがちな畑は紐を張っておきます。
カラスは最初は気がつかないのですが、
張ってあることはすぐにわかるようで、
飛んできても引っかかることはありません。
けれどカラス除けの効果はあります。
メロンの交配
黒沢進さんのメロン畑に今年もミツバチが来ていました。
運ばれてきても5日間位は警戒して巣からは出ないそうです。
今では我が物顔ですが。
交配自体は10日もあれば終わるのですが、
それ以降、メロンの花がある限り、
花があるうちは蜜が採れるので、おいて置いて欲しいと頼まれるそうです。
伸び盛りです
気温が高く、まだまだ種芋が元気なので、
苗が伸び盛りです。
定植(畑に植える)用の苗と頼まれている苗を切るのが精一杯で、
定植が間に合わないほどです。
ツバメの雛5羽
この前温めていた卵が孵ってしました。
5羽の雛がいます。
親鳥が餌を運んでくると、
巣から落ちそうな位身を乗り出します。
野菜の間引き
今年は農園前の畑は休耕していますが、そこの一角で自家製野菜を育てています。
10種類以上育てていますが、この時季は葉物は播種するとすぐに伸びてきます。
間引きしてサラダや汁物の具にしています。
【SPAC演劇】Jerk 演出 ジゼル・ヴィエンヌ

1970年代のアメリカ テキサス州で、10代の若者が27名殺害されるという事件の犯罪者達の行動を非常にリアルに再現した心が大きく揺れる演劇です。またその手法に驚嘆もします。
役者ジョナタン・カプドゥヴィエルの一人芝居ですが一人で6役を賄います。ジョナタン本人は共犯者デイヴィッド役を演じますが、主犯のディーンともう一人の共犯者のウェインと、被害者3名を、人形を使ってジョナタンが演じます。ですからデイヴィッドがこの演劇の進行役兼主役で、デイヴィッドと両腕の人形、それに加えて腕の人形が掴む人形が登場人物になります。それぞれの役は声色を替えて腹話術を使い、ジョナタンが演じ分けます。
一人の演劇、人形での演技では細かい設定の説明はできないことから、観客は配られた冊子で事件現場の背景を把握してから芝居がはじまります。
まず第一幕は、ディーンの殺害の再現からはじまり、ウェインがディーンを殺害してしまうまでです。
その後舞台が変わることから、もう一度冊子を読み次に進みます。
第二幕は、ウェインが次の被害者のブラッドを殺害し、最終的にデイヴィッドが決着を付けるためにウェインを殺害してしまうまでです。
そしてデイヴィッドの告白で事件の全容が明らかになり、この演劇でも再現されたことを説明して終わります。
ディーンは被害者を滅茶苦茶にし、犯しながら人を殺めます。そして被害者を自分の見立てた人物に変えて嬲る。言葉ではしっかりと説明ができないですが、言葉にまとめるとこうなります。
そしてその傍らでは、デイヴィッドとウェインの同性愛のセックスが行われています。これらだけでも衝撃なのに、カメラまで回っています。
これらの一連の出来事を、デイヴィッド本人としてと、人形と数種類の声色での台詞でリアルにジョナタンが再現します。リアルというのは、観客が思い描いてしまう心の中の情景がリアルということです。
この演劇が周到なところは人形劇だから大筋を表現しているだけなので、現場の状況の様子は観客の頭が描くところです。もし映像であれば目を背けたくなるような動きや台詞でも、観たことで納得しようとする、納得して体に纏わりついてくる恐怖や違和感を過去にしようとするのですが、この手法だと、殺人現場は自分で作った像なので映像よりも心に残るのです。
園子温監督の映画「冷たい熱帯魚」でもかなりおぞましい描写がありましたが、私はJerkの方がはるかに気分が重くなりました。こちらは殺人と死体損壊に加えて、ディーンの、殺人が快楽になり常習していくことも描かれているからもあるからですが。
人を憎んだり恨んだりは誰もが持っている感情です。だからと言って通常それが殺人に繋がることはまずありえません。しかし殺人者が、それらが動機だったと説明したら想像ができないことはありません。
けれどこの惨劇は彼等3人が楽しみながら犯しています。その気持ちは全く想像できません。
ただ、27人もの被害者が出たことは、ディーンは人を嬲りながら犯しながら殺人をすること、被害者を違う人物に見立てて葬ること、それをすることで彼の中に強烈な快楽が起こっていたのではないかと推測しました。そうでなければ理解できません。
いくつもの禁忌を破ってしまうことに加えて、他人のアイデンティティーを破壊する行為にこの上ない享楽があったのではないかという推測です。
ウェインがディーンを殺害した時も、ブラッドを殺害した時もそれを匂わす表現がありました。そして恐ろしいことに、ウェインはディーンの代わりの怪物になってしまったことも見逃せません。
この事件が起きたことに深く悲しみ、それを心の中で再現したことの動揺もありましたが、鑑賞後に、私が我を重ねてみてという観点から振り返ってみたら、とてもショックを受けたことがありました。
“人間には他人のアイデンティティーを破壊することを好む性癖があるのではないか”ということと、殺人の快楽がディーンからウェインに伝播したように、その行為はある者が行うと別の者に伝播していくのではないか?と私の中で仮説になったことです。
自分勝手に他人を見立てる行為は軽い気持ちで行ってしまいます。しかもそれを面白おかしく人前で披露することも取り立てて珍しいことではありません。個人的な話になりますが、自分の思い込みで他人にあだ名を付ける、という行為は何度となく行ってきました。
考えてみるとそれも、他人のアイデンティティーを侵食することに他なりません。
そして下手に誰もがそれを認めることになるとそれが伝播します。
この演劇の主犯ディーンも共犯のデイヴィッドもウェインも全く共感できないし理解しがたい人物だということは変わりませんし、許せない犯罪です。
けれど自分とは全く違う人物であるということに捕らわれていたのではないかとも思いました。罪もないことではあっても人を傷つけることで快楽を得ようとしている自分がいることに気づいたからです。またひとつ嫌な自分を見つけました。
けれど見つけた価値はとても高く、気づいてよかったとも痛感しています。
【SPAC演劇】タカセの夢 演出 メルラン・ニヤカム

世界を代表する一人の少年と九人の少女が、
大人になり老いていくのですが、私達は彼と彼女らにどんな社会を提供しているのでしょうか、と問うてくる演劇です。
スクリーンには、平和に尽くした人々から、犠牲になった人達や、
現在の都市(東京)の状況、そして少年少女にとって当たり前にあるはずの牧歌的なイメージまでが映されます。
それに合わせて彼等は、ミュージカルのように歌い踊ります。
それが全編全力なのが印象的です。
まるで、
僕等はこれ程までに一生懸命に生きていると伝わって来る程の熱気を帯びた姿です。
劇中のダンスは世界各国の基本的なものでしょう。
子供の頃の遊びも挟まれますが、彼等の成長の比喩であるとともに、「かごめかごめ」や「ずいずいずっころばし」等の日本のものが中心で、これらは観客に共感を呼びかけやすい配慮です。
また最初の衣装から10人が十人十色で、世界を象徴していることを示唆していて、彼等の成長期も老いてからもそこに繋げていることからも、観客である私は世界中の子供達とどう関わっているかを考えます。
大袈裟にそういうことを考えるというよりも、どんな気持ちでいるかを優しくでも、真剣に考えるように促される、そんな舞台でした。
タカセというのは、紅一点の反対の唯一の少年の役名です。
彼が夢見ているものは、もちろん世界が仲良くなることですが、
この演劇では、最初に観客と触れる場面があります。
その時からちょっと大きめのトランクバッグがキーになっていて、終盤には、そのトランクバッグには、彼の人生の全てが詰まっていることがわかります。
その中身は、みんなが仲良くなるための道具でした。
そして、それを介して少年少女時代に仲良かった10人が、大人になり離れ離れになっていたけれど、また仲良くなります。
そこでこのお芝居は本来なら終了ですが、カーテンコールで、観客も巻き込んで劇場が一体となる憎い演出があります。
これこそが、タカセの夢です。
夢とは実現していない状況です。
この演劇に“夢”という題名が付いていることを受け止めなければなりません。
【SPAC演劇】マネキンに恋して”ショールーム・ダミーズ” 演出 ジゼル・ヴィエンヌ

一人の男と、マネキンに扮した女優が器械的な踊りだけで表現する演劇です。
本当に踊りだけで台詞は一切なし。唯一劇中に歌が挟まれるだけです。
舞台には十五体以上のマネキンがいて男とともに七体のマネキンが、
一人で踊ったり、男と戯れたりします。
マネキンは皆極端な身なりや踊りです。
濃い化粧、高いヒール、体のラインを強調した衣装、
意志はないけれど、与えられた役目をキッチリとこなす踊りを見せるマネキン達、しかも個々に個性的です。
観客、特に男の観客の気をひこうとする仕草の踊りで演劇は始まり、
そこから男との戯れやマネキン同士がぶつかるようになっていきます。
一見は成長しているようですが、機械的です。
だから意志があるようには思えませんでした。
でも知性は育っているようです。でも感情はどこまでも封印されています。
だから意志とは、知性だけでは全く機能しないと改めて痛感します。
題名は「マネキンに恋して」ですから、男とマネキンの愛を描いているのですが、不毛に見えます。
演劇後のアフタートークで、
原作は男が月の光を受けた彫刻を見て恋したことをモチーフにしていると知りました。
すると、やはり男が女に対しての憧れと期待をマネキン達に求めていたことになります。
すると、この演劇は私個人として腑に落ちてきます。男が理想の女像を求めた世界です。だから複数の違う個性のマネキンが男と戯れます。
男は時に親密に、時に乱暴な振る舞いです。また、マネキンを動けなくしたりもしますし、操ろうともします。
隠していたい欲望が垣間見れたり、優しく振る舞う姿も見せます。
でも男はやっぱり操作した支配では、マネキンに息は吹き込めなかった。そう映りました。
「マネキンに恋して」は、ロマンチックな男が味わう現実を表現した演劇ではないでしょうか。
追伸
5/21は「小満」でした。二十四節気更新しました。
ご興味がある方は、干し芋のタツマのトップページからどうぞ。
干し芋のタツマ
二十四節気「小満」の直接ページはこちら
小満
アメイジング・スパイダーマン2 2014米 マーク・ウェブ

3Dの吹き替え版で鑑賞しました。
強い意志と正義感で必死に社会に尽くすスパイダーマンに対して、
嫉妬し、嫌悪を感じる人びとが出てきます。
社会に生じてしまうルサンチマンがテーマかなと、最初は考えながら観ていましたが、
そうもそうではないようで、
次には、恋人の亡き父親との約束(愛している恋人を一緒にはいない約束)と、
自分との葛藤を主にしているかな、と思ったのですが、それもスルーで、
ストレートな恋愛物語なんだと見ているとそうでもなく、
主人公は両親と不可解な別れを経験しているようなので、
両親からの自律が主題かなとも感じていましたが、
それが掘り下げられるようでもない。
そこであまりそんなことを考えずに鑑賞しましたが、
それが正解だったようです。