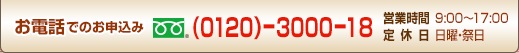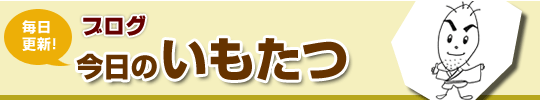芋日記
メロンの定植

メロンは大変です。
約一ヶ月かけて苗を作ります。
(こことは別にビニールハウスの苗床で)
その間に畑の準備です。
昨秋に蒔いた麦=風除け=が育つ頃から、
土作りです。何度か耕運し肥料を入れます。
その後は畝を作ります。畝にはマルチと呼ばれる
ビニールが敷かれています。
その上をトンネルという小さいビニールハウスを張ります。
やっと定植の準備ができました。
ここからが本番です。
毎日温度管理のために、天候をみて、
朝トンネルのビニールを上げ、
夕方はぴったりと閉めます。
もちろん天候により開け方も違うし、時間も違います。
とにかく、全部のトンネルの管理が最低一日2度以上あり、
開け閉めがあります。
「メロンやっている間中はどこにも行けない」
ということです。
メロンが美味しいのはあたりまえと痛感します。
【芋日記】
伏せこみ

さつま芋の種芋を植えて苗を作るのですが、
種芋を植えることを伏せこみと言います。
さつま芋の苗を育てるためには、外気温では低いために
ビニールハウスの中で種芋を育てます。
たい肥を入れて耕運しておいてから種芋を並べます。
その上からまたたい肥をかぶせます。
水と温度を保てば一ヶ月少しで苗が出来てきます。
【芋日記】
麦間栽培その後

ほしいもがおやつ、お遣いもの、という前の
保存食であったころは、麦の間にさつま芋を栽培していました。
秋に麦を植えて初夏に収穫です。
しかし、さつま芋の苗は麦の収穫前に植えなければなりません。
そこで、麦を植える間隔を広くとり、
その間にさつま芋の苗を植えます。
昨秋一箇所の畑でそれを試しています。
その麦が冬が明けて伸びてきました。
ここから一気に伸びて、分けつしてゆきます。
出穂しているときに定植と目論んでいますが、
どうなるか楽しみです。
【芋日記】
釜仕舞い

ほしいも農家の中で今でも、数軒ですが、
薪を焚いてさつま芋を蒸かしてる農家があります。
その中の一軒が昨日で今シーズンの蒸かしが終わりました。
この農家では毎年、最後の蒸かしが終わると、
釜とかまどにお神酒とお供えをします。
良い習慣で感心です。
釜もかまども頑張った農家さんも
無事に終えてお疲れさまでした。
お供えは毎年変わります。
今年はお赤飯でした。
わたしもお相伴させて頂きました。
【芋日記】
オリジナルほしいも3

タツマならではのほしいも
タツマにしかないほしいも
を詰め合わせた「オリジナルほしいも」
今月末に販売予定です。
今日もその話題です。
通常の平ほしいもの1.5倍以上の厚さにスライスした厚切り
名づけて「大判」
仕上がりも普通の平ほしいもの2倍かかります。
【芋日記】
オリジナルほしいも2

オリジナルほしいもには、
紫芋ほしいもも詰め合わせの予定です。
そこらじゅう まっ紫になりました。
安納芋のオレンジとの対比が鮮やかです。
まだまだタツマならではの
オリジナルのほしいもを販売に向けて作ります。
【芋日記】
オリジナルほしいも1

今月下旬に発売を予定している商品
「オリジナルほしいも」は、
タツマならではのほしいもを詰め合わせます。
その中のひとつが
「安納芋ほしいも」です。
安納芋は肉質がもろく、繊維質があるので、
ほしいもに加工しにくい品種のさつま芋です。
皮むき、スライス、ひろげ、が やりづらいこと。
悪戦苦闘で製造中です。
【芋日記】
干し場の崩壊

昨日未明からの大荒れの天気で、
干し場に大ダメージを受けました。
ビニールハウス2棟が無残にも・・・。
干してあった干し芋が少なくて幸いです。
干し場一杯だったらと考えると、ぞっとします。
いつも天気予報は気にしているのですが、
ついつい甘くみてしまいます。
それと、自然の恐怖も甘くみています。
バスも電車も仕事も学校の授業も、
何からなにまで時刻どおりきちっとなんて、
実は自然が静かな条件下なんですよね。
【芋日記】
差し入れ

男やもめにウジがわき、女やもめに花が咲く
のごとく、
茨城にいるときは名ばかりの自炊をしています。
タツマは米屋でもあるために、
なんとかご飯は炊きますが、それだけ。
それを知ってる親しい ほしいも農家がよく
おかず(おつまみ?)を作ってくれます。
今回は、煮物。
サトイモ、イカ、ニンジンです。
こういうの本当に嬉しいですよね。
普段スーパーのお惣菜に頼っているのでなおさらです。
これにおせんべと漬物付きでした。
(好みをすっかり知られています)
今、真冬のこの時季は、ほしいも仕上がりの最盛期。
忙しい中スーパーに買出しに行けそうにない日でしたので、
特に嬉しく書き込みました。
ひとりごとでした。
【芋日記】
小麦2

播種から約2ヶ月、
芽が出たのを確認に来てから約1ヶ月、
ほとんど変わりはありません。
今が寒さのピーク、
芽だけを出して“じっと”しているようです。
春本番を迎えると“ぐっと”伸び始めます。
動物が冬眠するのと同じなのでしょうか?
半年後に子孫を残すために、今があるということです。
先がわかっていると、今が耐えられます。
自分が今耐えていないとしたら、
先をみようとしていないのでしょう。
【芋日記】