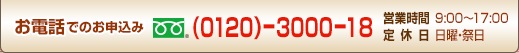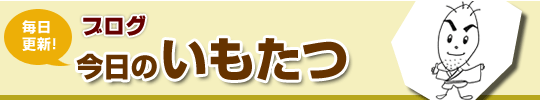- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
芋掘りではつきもの
芋掘りしているとバッタを追いかけている感じになります。
そういえば、稲刈りの時もバッタをよくみかけます。
意外と、寒くなっても生息しています。
マリーゴールドの鋤き込み
思いのほか大きくなったマリーゴールドは、
他の緑肥作物のように、トラクターで鋤き込むわけには行かないほど育ちました。
つる刈り機で上を刈って、根の部分は何回かにわけて土となじませます。
この畑は休耕したのですが、試験的に半分だけマリーゴールドで土壌改善しました。
かなり手間がかかるので、効果がある事を期待しています。
【SPAC演劇】舞台は夢 フレデリック・フィスバック演出

主人公のクランドールは、誰が見ても己が望んだ生き方でした。愛に忠実といえば聞こえは良いですが、愛の他には何も見えない生き方です。
では、それにつられる他の人物はどうかと言うと、彼を追う3人の女性も、彼の父プリダマンも、彼に振り回されながらも、実は彼と同じく己が望む生き方であって、人は自分のやりたいことは自分ではわからないものということでしょう。
プリダマンに厳しい躾を強いられることから家を飛び出したクランドール、10年経っても消息がつかめないことから、プリダマンは魔術師のアルカンドルにわが子を探して欲しいと訪ねます。
アルカンドルは今のクランドールが生きる実際を洞窟の中でプリダマンに見せる力がありました。するとクランドールは、マタモールというほら吹き隊長に仕える身でした。
マタモールは愛するイザベルに想いを告げるために、クランドールに託しイザベルの下に送り出します。
しかし、クランドールとイザベルは愛し合ってしまいます。イザベルにはアドラスト男爵との結婚が決まっていました。それを反故にするイザベル、当然諍いが起こります。
クランドールは過ってアドラストを殺めてしまい、牢獄へ、死刑判決です。
クランドールの運命は絶望的ですが、その時にイザベルの侍女のリーズの機転で、牢番を味方につけて、クランドールは牢獄から脱出です。イザベルとリーズと牢番の4人で生きる仕切り直しです。
数年後、領主に仕えるクランドールとイザベル夫婦、しかしクランドールは領主の妻のロジーヌと愛し合う関係になってしまいます。
それに勘付いた領主は、クランドールとロジーヌを亡き者にすることにします。それが決行されました。嘆くイザベルとリーズ、そしてそれらの一部始終をアルカンドルの力で俯瞰していたプリダマンも絶望します。
ところが実はクランドール達は生きていた。なぜなら・・・。
アルカンドルとプリダマンが俯瞰しながら、クランドールを中心に演劇が進みます。
基本的には悲劇ですが、狂言回しのマタモールがいることで、喜劇っぽくなります。最期のどんでん返しも悲劇を覆します。
マタモールは筋金入りのほら吹きです。出任せ以外は口から出てこない、しかも大法螺吹きです。誰も相手にされません。仕えているからばかりクランドールは従います。
しかし憎めない。なぜなら、彼は私の中にも居るからです。
彼は心の奥底には自分がほら吹きだという自覚がありますが、今ここに居る時の自分、ほらを吹いている自分は、しゃべっているその強がっている人物そのものになりきっています。また、そうでなければ今を生きられないのです。喜劇を演じる悲劇の人物です。
彼以外もそんな人達の人間模様です。
イザベルはクランドールを愛し続けます。アドラストと結婚した方が裕福で幸せになれますし、愛する父親を棄ててまでクランドールを取りました。最期にはクランドールに裏切られますが、ロジーヌとの仲を引き裂くことも結局はしません。領主の妻を奪うことで仕打ちを受けるクランドールの身を案ずるほどです。そして、クランドールがロジーヌを本当に愛していることを知ると彼を許そうとします。また、クランドールが死ぬと後を追おうともします。
イザベルは彼に献身したのに、裏切られる仕打ちを、その怒りを彼にぶつけますが、彼女もそんなクランドールを愛したことは己が望んだことだと気付きます。
この構図はリーズも同じです。
リーズはクランドールを牢獄から助け出すのですが、それには逡巡がありました。彼女もクランドールを愛していたからです。またクランドールもイザベルを愛しながらもリーズを愛していて、彼に、妻はイザベル、リーズは愛人として愛するとまで言われていました。
けれど、リーズはクランドールを助けます。
しかも、牢番を彼女の虜にしてという方法をとります。その代償は牢番と結婚することになるのですが、それをも受け入れます。それほどクランドールを愛したのです。
リーズもまともではないのではないかと思えますが、彼女も生きたい生き方をしました。
プリダマンも同じです。クランドールのためを思って厳しく躾ましたが、行方知れずになり、心配でしかたがありません。アルカンドルを頼るのは、もちろんクランドールのことが心配だからですが、自分の心が探さずにはいられないのです。
もうクランドールは彼が生きたい人生を歩んでいます。でもプリダマンは息子の心配をする生き方がプリダマンの生き方なのです。
クランドールが死刑になる時も、領主の手に落ちた時も絶望します。親として当然ですが、どこまでも息子を追う姿は自律した姿ではありません。でもそれがプリダマンの生き様です。
クランドールは、お世辞にも褒められたものではありません。同時に何人もの女性を愛するのですから。しかも、その行為に悪びれたところが全くありません。自己に忠実なのです。
あまりにも自分を飾る生き方を身につけてしまっている私達に異を唱えているかのようです。原作ができた17世紀のフランスは、自分の愛に忠実なのが当然だったのか、その時代も社会に取り込まれて自己を隠してしまう風情だったのか、ただ、どちらも人が持つ普遍的なものだということでしょう。
この演劇は、アルカンドルとプリダマンが俯瞰するという構図で繰り広げられます。その時点で観客は俯瞰視点になります。しかも、プリダマンがクランドール達を見ている姿が舞台上の大きなスリーンに映るのです。だから劇中の人物に想いを入れながら少し冷静になります。それが最後のどんでん返しにも活きてくるという構造は見事です。
そして演出もそれを考慮に入れられています。
面白い演出として、先ほどのプリダマン達を撮るカメラが場面によってはクランドール達を捉えながら劇が進むことです。役者の顔のアップが大きなスクリーンに映し出されます。そしてもちろん観客は演じる役者そのものと、大きなスクリーンの姿と両方を観ることになります。
この演出は主に登場人物の内面を吐露するところと、ラストのクライマックスのクランドールとロジーヌの密会のシーン、ここでクランドールとイザベルのこれまでの愛と各々の愛についての語らいと、同じくクランドールとロジーヌの愛の語らいで使われます。
観る者は登場人物の内面の痛みをひしひしと感じる演出です。
演劇後のアフタートークでも話されていましたが、役者さんたちは、かなりカメラを意識するようです。マイクも口元にまできて、普段の舞台上の体一杯、声一杯に使った表現とは別の演技とのことです。
登場人物の内面を静かな声で、でも我々にはマイクを通した大きな音量になることで、その場面の揺れる心理がより伝わり、そして大きな気持ちの揺れであることが伝わってくる演出だと思いました。
また同じくアフタートークで、演出家のフレデリック・フィスバック氏から、自分の心の内面を素直に出す、自分に嘘を付かないでの演技を求められたとのことです。
なるほど、この演劇のテーマの、自己が求めている生き方を見つめるに沿っているし、人との関係で進むこの劇には適切な演出になるのだと納得しました。
喜劇を帯びた悲劇で最後はほっとする、楽しめる劇を、シンプルな舞台ででもスリリングな演出になっていたspacの「舞台は夢」、堪能しました。
追伸
10/2に、10月の「毎月お届け干し芋」出荷しました。
今月のお宝ほしいもは、“有機紅あずま平ほしいも”です。
ご興味がある方は、干し芋のタツマのトップページからどうぞ。
干し芋のタツマ
毎月お届けの「今月のお宝ほしいも」の直接ページはこちら
今月のお宝ほしいも
試し掘りしました
大きくなりやすい品種を植えた畑数箇所を試し掘りしました。
大きさが区々な畑もありましたし、全体的にもう少し大きくしたい畑もありました。
この畑は、大きく育つまではいっていませんでしたが、
肌が綺麗な芋が多かったです。
ほしいもの原料芋ではこれがとても重要です。
舞台は夢 コルネイユ作 井村純一訳

SPACの「舞台は夢」の観劇があるので、原作を抑えようと読みました。
面白い戯曲でした。演劇が楽しみになった反面、読んでない方がドンデン返しを楽しめたかもという効果も少し。
色々な演出で上演されている訳がわかる痛快な話です。
落語に出てくるような人物がいたりしますが、私は落語の登場人物は、ちょっと強調された普通の人だと思っていますので、この話の人物も、決して誉められない輩が多いですが、自分と重ねてしまいます。
それよりも、入れ子構造になっている点と、魔術師を登場させて主人公の父親が息子のことを心配し、魔術師に息子の動向を見せてもらうという構造が、戯曲全体の俯瞰になっていて、登場人物一人ひとりを注視できるところが優れています。
そして最後がまた痛快です。
SPACの「舞台は夢」はどんな仕上がりか、観劇が待ち遠しくなりました。
状態をみて後回しにしました
休耕している畑の、土壌改善の緑肥作物は芋掘り前に畑に鋤き込みますが、
この畑は後回しにしました。
まだ勢いがあるので、収穫後に鋤き込みます。
さあ収穫です
稲刈りがなんとか9月一杯で終わり、
10月は芋に取り掛かります。
ここから春まで、干し芋農家はどこも多忙になります。
状態をみて後回しにしました
休耕している畑の、土壌改善の緑肥作物は芋掘り前に畑に鋤き込みますが、
この畑は後回しにしました。
まだ勢いがあるので、収穫後に鋤き込みます。
整備をしています
つる刈り機に続いて、
サツマイモの掘り取り機の整備と取り付けです。
収穫まで待ったなしになってきました。
作付けは多くないので
遅れていた稲刈りですが、ここにきて挽回しています。
ほしいも農家は、そんなにたくさん稲作していないのと、
コンバインの性能が上っているからです。