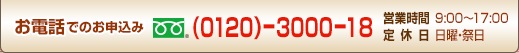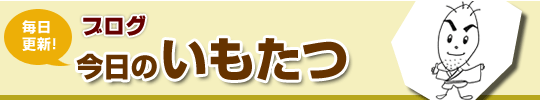- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
再来年の準備です
有機農法での干し芋用のサツマイモ栽培を続けてきて、
解ったことのひとつに、
連作はご法度ということです。
この畑は今年作付けしたので来年休耕ですが、
輪作の麦を蒔きました。
麦は収穫しませんが、土作りのためです。
再来年の準備です。
畑の様子で改善の方法を考えます
来春の作付けは一年以上前から土作りをしていた畑を使います。
今年収穫した畑は最低1年は寝かせます。
寝かせると同時に地力の回復・改善を図ります。
輪作の麦を蒔く畑
緑肥作物を使う畑、
その両方、
それにより、冬は寝かせる、いや寝かせない等、
どの方法をとるかは、今年の収穫状況で異なります。
雉が逃げ込みました
ほしいも産地にいると、
畑にいる虫等の小動物を捕食している雉と、
結構な頻度で遭遇します。
大きい体の割りには狭い場所に上手く隠れます。
さらば友よ 1968仏 ジャン・エルマン

アラン・ドロンとチャールズ・ブロンソンの友情映画で、
エッセンスとして二人が追い込まれるサスペンス、
濡れ衣を着せられて・・・どうなるか。が加えられています。
前半は終盤に向けての準備で、
中盤の二人が地下室の金庫破りをするところで、
二人の友情と物語の要素をすべてそろえて、
終盤の盛り上がりに向かいます。
そして二人ともカッコイイで完結です。
アラン・ドロンの各シーン、チャールズ・ブロンソンの各シーンが味わい深いです。
アラン・ドロンはモテテでもクール、ヒロインを抱き上げるシーンなんかは、
彼のファンにはたまらなかったでしょう。
チャールズ・ブロンソンの満たされたグラスにコインを入れるシーンや、
女衒のようなことをやるシーン等も見応えがある演出です。
公開当時10代、20代だったら、二人のマネをしていたかな。
なんて想像してしまう位、カッコよかったです。
お茶漬けの味 1952日 小津安二郎
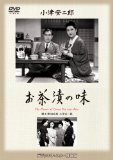
またしても小津安二郎の映画は素晴らしいということを描くことになりました。
他の作品とは舞台設定も役者も違うのですが、
底流に流れる、人は尊い存在だという哲学は同じです。
そして、かなりの年月を経た夫婦は涙してしまいますし、
これから夫婦になるカップルにはぜひ鑑賞して欲しい作品です。
一流会社に勤める部長職の夫ですが、職以上の暮らしぶりです。
どうも妻が上流階級の出だということが裕福の根本です。
主な登場人物は妻の姪21歳、妻の友人二人(同じく金持ち)、
夫の後輩(金持ちではない)、パチンコ店経営の夫の戦友です。
妻は夫にかなりの不満があります。
夫を小馬鹿にして、平気で嘘を付き、友人たちと修善寺旅行(贅沢の象徴)も茶飯事です。
夫は寡黙ですが、芯の強さ優しさが漂います。
夫の後輩と姪のデートがラストシーンですが、
そこでのキーワードが「男の頼もしさ」ですが、この台詞そのものの男です。(佐分利信が名演です)
妻は夫が気に入りません。安いタバコを吸うこと、お味噌汁をご飯にかけて食べること(妻は、犬みたいと表現します)、三等車の方が落ち着くと言うこと、とにかくそれらの表面が自分とは違うからです。
そして自分との価値観の違いをなじることで(暇な)生活のバランスをとっています。
でもどこかでそれは不安定だと気づいています。それを解消する方法は、素直になるか、徹底的に夫を懲らしめるかです。
ある時姪が見合いをすっぽかしました。姪は見合い結婚の(主演の)叔母夫婦のようになりたくなかったからです。姪の見合いの面倒を見ていた妻は苛立ちます。しかも夫が姪を庇うのだから、夫への怒りが最高潮に達します。
これがきっかけで、夫と絶縁状態、といっても怒っているのは妻だけです。
夫は南米へ単身赴任の辞令を受けていました。急遽旅立ちになりますが、妻は怒って神戸に一等車に乗って遊びに行ってしまい、南米行きを知りません。夫は電報で呼び出したが妻は無視。実家と友人の電報で事態の深刻さを知り戻りましたが、時すでに遅く夫は機上でした。
ここに来て妻の後悔が始まります。友人から我侭を言われ続けてきた意味がしみじみと身にしみます。その妻へ神様がプレゼントをしてくれました。
飛行機のエンジントラブルで夫を妻の下へ一晩だけ戻してくれたのです。
ここから、(結婚して何年経っているのか、15年から20年近いか)
結婚して初めての夫婦二人の夫婦になる誓いの行動を起こします。
それは神聖な儀式のような美しいシーンでした。
(小津作品の中でもかなり印象に残る名シーンです)
妻は夫に心からの謝罪をします。夫の頼もしさの中で生きていたから安堵だったことに気づいたからです。
夫も一番愛している妻に愛された安堵感で一杯になります。
妻は数日後にいつもの友人達を姪に言います。「(夫の)嫌なところが全部好きになった」と。(木暮実千代が名演です)
多分、妻はこれからも夫に嘘もつくし、遊びにも行くでしょう。すぐに怒ることも変わらないでしょう。でも全然違う心境でしょう。
長い年月夫婦でいると、嫌な面ばかりを見るようになります。そして見たことで嫌という感情が湧き、それを相手にぶつけます。
でもそれは相手を信頼しているからできることです。
そこがわかれば幸せです。何か変わらなければ幸せになるなんてないのです。
今、夫と(妻と)いて嫌になったとしたらそれは自然な感情で、それをぶつけることができたとしたら、『その相手は、かけがえのない存在だと心から思える』かどうかだけです。
これを諭すために、すべてのシーンも台詞も役者の選定もセットもロケも、多分まだ気づいていないシーンも、あったという映画です。
素晴らしい作品でした。
追伸
『プレミアム干し芋セット2013』販売開始しました。
ご興味がある方は、干し芋のタツマのトップページからどうぞ。
干し芋のタツマ
『プレミアム干し芋セット』の直接ページはこちら
プレミアム干し芋2013
第七の封印 1956瑞 イングマール・ベルイマン

時代は中世ヨーロッパ、十字軍の遠征から帰還した騎士、
疫病が流行る世紀末、この世の終わりを思わせる冒頭からのシーン、
そこに騎士を迎える死神が現れます。もちろんお迎えです。
騎士は死神にチェスを挑みます。
勝てば生きながらえることを条件にします。
どこかあどけない死神は、それを承知します。
ロードムービーのように騎士と、彼に着いていく者達と死神の旅が始まります。
疫病で苦しむ人々、魔女狩りの少女とのやりとりから、
神の存在を懐疑する騎士です。
そして彼には死神が付きまといます。
神の存在を問う騎士、それに反して騎士と同行している旅芸人の親子(夫婦と幼い子供)がいます。
彼ら(正確には夫だけ)は、暗黒の世とは無関係な生き方をします。考え方ともいえます。
彼には死神が見えます。マリア様も見えます。けれどだからと言って怖れもしないし、
救いを求めることもしません。
ただ飄々と日々を営むのです。
生きるとは?死とは?を命ある限りそれを自己が納得するまで追及する騎士と、
全く正反対の旅芸人の二人の姿から生きる意味を探ってしまいます。
どちらの生き方をしているのかではなく、
どちらも自分の中にあります。
ただし、自分の都合の良さを優先して、どちらかの自分を肯定させているのではないかと、
思うばかりでした。
ラスト、踊るようにして死神に連れられる騎士達、
この世で旅を続ける旅芸人の親子、
最後も対照的でした。
ここも選択権が自己にあり、自己にないことを感じるシーンです。
己で如何ともしがたいことが確かにあります。(死もそのひとつです)
けれどだからと言って選択権がないわけではない。それを強く感じました。
どれだけ我慢して収穫しないかが大事
高品質の干し芋作りの第一歩が、
「良い原料芋だけを使う」です。
当たり前ですが、これが中々難しい。
畑で掘り起こした芋は、苦労してやっとできたという想いから、
どうしても少しでも多く収穫したくなるのが人情です。
それをぐっとこらえて、
本当に良い干し芋になるものだけを選んで選んで収穫する。
それだけ畑に置いていくか。
選別しての収穫作業から干し芋加工は始まっています。
ティファニーで朝食を 1961米 ブレイク・エドワーズ

華やかなオードリー・へプバーンとは裏腹な、
孤独でやり切れなさを持って都会に住む主演二人が、
そこから抜け出せるかという物語でした。
田舎の生活が嫌で、しがらみを捨ててニューヨークで暮らすホリーは、
お金に執着していて、お金で夢を買おうと夢みています。
売れない小説家のポールは、パトロン頼りで小説を書いています。
それ自体を仕方ない行為と割り切っています。
その二人が出会って、恋をして、という話です。
結論はハッピーエンドですが、前途多難でしょう。
今の自分と成りたい自分、成れると真剣に考えている自分像、夢見ているだけの自分像、
決して直面していなくても、それらと折り合いをつけているんだな。
と感じました。
芸達者な猫が重要な役で登場します。
この猫は「名前がない猫」です。飼い主のホリーはいつも「ネコ」と呼びます。
ホリーは中々ホリーを見つけられないということなのでしょう。
銀河星プラスEM栽培の結果
土壌改良に優れたたい肥「銀河星」と、
EM農法を取り入れた栽培を試しています。
安納芋と兼六人参芋で2年間試してみましたが、
成功とはいえない感じです。
一株でたくさんのサツマイモが成るのですが、
ひとつひとつが、干し芋に加工するには小さいのです。
品質は良いのですが、それが障害になっています。
来年はもう一工夫してみます。
作付けが少ない「ほしキラリ」
玉豊に追いつき追い越せが合言葉で毎年のように新しい品種が登場しています。
「ほしキラリ」も数年前に登場した品種です。
高品質の干し芋に仕上がるのですが、
収穫量が少ないために普及していません。
タツマの有機農園では、「ほしキラリ」の美味しさは魅力なので、
作付けを増やしています。