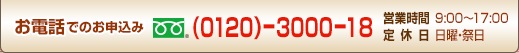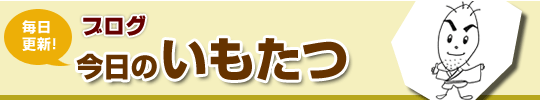- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
土壌検査用の土
毎年作付け前に管理している畑の土壌検査を行っています。
20近くの畑から、4隅と中央の土を採取して、
カラカラに乾かします。
その結果を踏まえて今年のその畑に投入する、肥料等を決めます。
これまで積み重ねてきた結果の定点観測にもなっています。
海に遠いほど
ほしいも産地は太平洋岸沿いに位置しています。
産地のどこにいても、寒流の影響で冷たい海風が吹いていますが、
海に近い畑と、遠い畑では風の影響が異なります。
昨秋同じ時期に蒔いた麦も伸び方が全然違います。
メロンがポット苗になっていました
種まきしてあったメロンは、芽が出てしばらくは苗床において置きますが、
ある程度育つと、苗床の土ごとポット苗に移植します。
本圃場に植えることを見越してです。
種まきは遅れましたが、その後は順調に育っています。
キャベツを頂きました
たかおさんの奥さんがキャベツとホウレンソウを切ってくれました。
大根も頂ました。
ほしいも産地にいると、野菜には事欠きません。
簾洗いと稲藁集め
干し芋加工の片付けもだいたい目処がたってきました。
500枚以上ある簾(すだれ)も洗い終わり、
干し場の敷き藁にしていた稲藁は、
踏み固められたものはビニールハウス脇の抑草として、
そうでないものは畑の抑草として集めました。
【SPAC演劇】真夏の夜の夢

演出 宮城聰 作 ウィリアム・シェイクスピア 潤色 野田秀樹
人はとかく物事を曖昧なままにしてしておきたいものです。
人は基本的に怠惰ですから、決めないことで責任が生じないことを選び勝ちです。それに曖昧にしておくと夢見がちでいられます。
「真夏の夜の夢」は、主人公の“そぼろ”が自分の心の奥、自分では気が付いていない自分の本音の部分を知る旅の物語ですが、自分の心の奥にある本心が何かなんて、曖昧にしておきたい最たるものです。
老舗割烹料理屋のハナキンの娘“ときたまご”は四日後に結婚式を控えています。相手は父親が決めた板前のデミですが、別の板前のライと相思相愛です。どうしてもライと一緒になりたいそぼろは、ライと「知られざる森」へ駆け落ちをします。幼馴染のそぼろにだけそれを告げました。そぼろはデミを慕っていたことから、駆け落ちのことをデミに伝えます。ときたまごを追うデミ、そのデミを追うそぼろ、4人は知られざる森で不思議な体験をします。
知られざる森は、妖精たちが棲む森でした。ちょうどその頃、オーベロン王とタイテーニア女王は、拾った赤ん坊が原因で夫婦喧嘩の最中でした。オーベロンはタイテーニアを意のままにするために妖精パックに惚れ薬を取ってくるように命じます。早速パックは出かけますが、途中で悪魔メフィストに捕まります。パックに化けたメフィストはオーベロンやタイテーニア王を騙した上に、二人からの依頼を受けて契約を取り付けます。この契約が破棄される時には人間の憎悪が増幅するというものでした。
ときたまごは、ライからもデミからも愛されています。それに対してそぼろはデミを愛していてもデミには嫌われています。森でデミを追うことすらデミに嫌がられるそぼろですが、ひょんなことから惚れ薬の効果でデミにもライにも突然愛されることになります。それを戸惑うそぼろです。
知られざる森とは、人間がそこに迷いこんで不思議な体験をしても森からでる時には人間は何も覚えていないことから名付けられました。そしてここには人が置き忘れたものがたくさんあります。
この森に棲む妖精は逆隠れ蓑を着ない限り人には見えません。だからここで起きたことは人は気のせいだと思っています。この演劇では気のせいは「木の精」という定義です。そして、「人は見えないものは信じない」ということもキーワードです。
私は、知られざる森はそぼろの深層心理で、表層から深層へとそぼろが辿っていく物語だと思いました。
迷い込んだ4人の若者達は表層の意識の中で、惚れ薬によって愛する人を代えてしまいます。そこは表層に近い願望です。
メフィストはそこから一歩踏み込んだ自分が知りたくない自分を知る案内人であり、そぼろが持つ悪の感情そのものでもあります。
そして、オーベロンとタイテーニアをはじめとした妖精は悪の感情のもっと奥の善意であったり生きる知恵で、森自体が奥深く広いそぼろの深層意識を現していると捉えました。
ライとデミは最初の惚れ薬でそぼろを愛し、ときたまごを憎みます。でもそぼろは、二人は自分を愛しているそぶりをして茶化していると思い込みます。
「人は見えないものは信じない」逆に言えば見えるものを信じるということです。愛を叫ぶ二人の男は見えるものですが、そぼろはその見えるものを信じませんでした。
だから、実は人には見えないものを信じる能力があるのです。しかし注意深くその能力を封じています。何故なら自分の本音に近づくからです。これはまだ序章で、この物語はこの程度の旅で終わりません。
ライとデミの二度目の惚れ薬ではなんと、二人が愛しあうことになります。それを解消するためにはメフィストの契約を破棄しなくてはなりません。契約破棄をすると、二人は憎み合い争いを始めます。これもそぼろの心です。デミを愛しているし愛されたい裏にデミを破滅させたい、また、ときたまごと上手くいっているライやときたまごに対してのルサンチマンです。
まだ続きます。メフィストはそぼろに言います。「言葉にしなかった言葉(飲みこんだ言葉)がこの森にはたくさんある」と。飲みこんだ言葉はその人の本音です。そして人に知られたくない自分だけが知っていると思っている感情です。一見、言わなかったことは他人には伝わっていないようですが、実は他人も気づいています。「人は見えないものを信じる力」がありますから。
これに関しての問題は、自分の悪の感情は他人には気づかれていないだろうということを自分に言い聞かせていることです。
メフィストが全部知っていたのと同じように他人も意識しないだけで知っています。ただお互いにそれを曖昧にしていたいので、言う側も言われた側も意識しないようにしがちなのです。
物語は、そんなそぼろの飲みこんだ言葉が森で具現化していきます。まさにそぼろの悪の感情が森に火をつけて森は焼き尽くされていきます。そぼろは自分の奥にある心がどんなものだったかを目の当たりにするのです。
そしてメフィストはオーベロンとタイテーニアの夫婦喧嘩の原因になった拾われた赤ん坊だったことも明らかになります。メフィストはそぼろ自身でもありますから、森に火を放ったのはメフィストであっても、焼き尽くすのはそぼろの奥の奥にあった本心であり、そぼろの心の叫びです。
でもこれは誰しもが生きてきた中で抱える、悲鳴をあげたい鬱屈した感情です。
この演劇は壮大な森を想わせるセットですし、衣装も楽しませる凝りようだし、音楽も照明も心を浮き立たせます。軽妙な言葉が飛び交い、また洒落の効いた言葉も飛び交う喜劇として楽しめますが、「あたしの精」「目が悪い精」「耳が悪い精」「年の精」等の登場人物の役名といい、これらの言葉を含めて少々毒がある言葉が台詞にも使われているので、一筋縄ではいかない喜劇だという感覚になります。
案の定で、そぼろを自分に置き換えて劇を観ると、逃げ出したくなります。自己の心にある嫌な部分が見えるからです。そして普段は、常にそれを見ないようにしていることも明らかにされるからです。
でも最後は、メフィストの涙で森の火が収まります。森を鎮めるメフィストの涙ももちろんそぼろの心の現われです。心の奥には悪意や悲しみだけではないし、人は悔いることも出来て純真な気持ちをいつでも持つことができることの表現です。
だから、嫌な部分を含めてもあなた自身には価値があると言ってくれているようでした。
自分の心の奥にある本心は、綺麗ごとだけではありませんから、日常で意識していることとは往々にして異なるものです。だからそれを観にいくのはあまり気が進みません。
けれどそれを観てそれを受け入れるのは大事なことです。普段意識していない自分の心を含めて自分自身なのですから、それを踏まえないと成りたい自分になんてなれるわけがありません。また、それを認めると自分にも他人にも今よりも優しくなれることも間違いありません。
演劇「真夏の夜の夢」は、本当の自分を観る勇気を与えてくれます。
農園前の畑
農園前の畑は4つのビニールハウスを備えていて、
干し場兼苗場です。
干し場は4棟全部使いますが、苗場は2棟を年により使い分けます。
今年も2棟を苗場にして2棟は休耕します。
休耕の2棟のうち1棟の一部では、自家製野菜を育てる予定です。
生食用のサツマイモ苗場
干し芋用のサツマイモよりも一週間ほど早く、
生食用のサツマイモ紅あずまの種芋の苗を作りはじめます。
その苗床作りの第一弾がはじまりました。
まずは水分を苗床に染みこませます。
稲藁集め
稲藁は重宝です。
干し場の足場に敷いてあったものは、
畑の抑草に使えます。
畑ではいくらあっても良いので、
稲藁を集めておきます。
有機サツマイモの苗場つくり
干し場の敷き藁を取り除き、苗場の準備に取り掛かりました。
1週間かけて苗床に仕立てていく予定です。
追伸
『有機干し芋セット2014』販売開始しています。
ご興味がある方は、干し芋のタツマのトップページからどうぞ。
干し芋のタツマ
『有機干し芋セット』の直接ページはこちら
有機干し芋セット2014