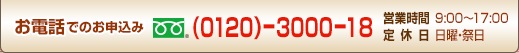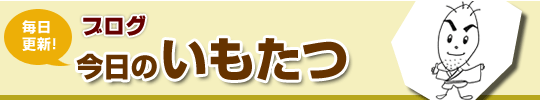- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
長い灰色の線 1954米 ジョン・フォード
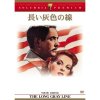
アメリカ陸軍士官学校「ウエストポイント」に
50年教官として勤めたマーティ・マー(主人公、タイロン・パワー)の
自伝映画です。
ウエストポイントは、
アイゼンハワー大統領はじめマッカーサー元帥等を送り出した
伝統ある名門士官学校のようです。
当時アメリカの誇りだったのでしょう。
(今もそうかもしれませんが)
製作がベトナム戦争前なので、
本当に良き士官学校として描かれているようにみえました。
このあたりは、郷愁がある者とない者で感じ方はかなり違うでしょう。
映画は、50年にわたる教官と家族、そして生徒たちとの交流です。
タイロンパワーは主人公の、長い人生を上手く演じています。
生徒が戦死して、その息子をまた教えるということの悲哀。
でもそれは、祖国のため。
このあたりの心の葛藤もいやらしくなく描かれます。
映画全体にユーモアある演出もあり、
ジョン・フォード監督の手腕がさえます。
もう一つの見どころは、
士官学校の生徒たちの演奏と行進が要所で出てくるシーンです。
映像も綺麗だし、使いどころも良いと思いました。
立川談笑独演会
*粗忽の釘
*天災
中入り後に新作落語の
*ジーンズ屋ゆうこりん
三本通して、泣かせの瞬間をつくるのですが、
そこに益々磨きがかかっています。
古典落語にそのエッセンスが、
談笑師匠ならではの“外し笑い”をとりながら入るところは、
新たな感覚です。
談志師匠が亡くなって半年足らずで、
まだまだ師匠とのことは語り足りないことも窺えました。
そこを枕に、
「粗忽の釘」で、エンジンがかかっていき、
「天災」は、紅らぼうなまるとのやりとりで、
談笑らしさ全開です。
「ジーンズ屋ゆうこりん」は、
こちらを視ながら塩梅をはかっています。
もちろん面白かったです。
強弱が上手いのと、
前から思っていたのですが、
談笑師匠は、
今まであまり注目されないところを掘り下げます。
古典落語でもそうですが、
新作のオリジナルでも感じます。
機会をつくってまた行きたい落語家です。
カルテンルードヴィッヒヴァイツェン
ヴァイツェンもかなり好きなタイプのビールです。
これもOKでした。
甘いのですが、遠い味と余韻で酸味があるので、
甘みが引き締まります。
香りももちろん良いです。
苦いビールも好きですが、
ドイツビールのヴァイツェンは、
全く違うジャンルで好みです。
そしてハズレがないですね。
麦間栽培の麦が伸びてきました
今年は、
*秋準備の麦間栽培
*春準備の麦間栽培
*マルチだけの抑草栽培
の3通りでの有機栽培をします。
その中の一番参考している、秋準備の麦間栽培の麦が伸びてきました。
暖かい日が後押ししています。
この様子だと、春準備の麦間栽培の麦も伸びてきそうです。
モミガラの使い道
有機栽培では自家製たい肥作りが不可欠です。
たくさんのたい肥を作っていることを知っている、
親しい農家が、たくさんのモミガラをたい肥場に運んでくれました。
もちろんたい肥にも使いますが、
畑の状態をみて、直接畑に入れることもありますし、
育苗の苗床にもモミガラは欠かせません。
種芋の保温材としても重宝です。
ありがたく使わせてもらいます。
畑の法面(のりめん)
畑は形も色々ですが、
高低差があるところも多く、
境が傾斜していたり、畑との境にたくさんの空間が出来ている所があります。
有機栽培は、その法面も農薬を使わないので、
年に数回手取りで除草していました。
それが大変なので、抑草のシートを敷こうと計画しています。
育苗ハウスの管理
苗が芽が出るまでは、温度は高め、水は最小限。
芽が出ると水は多め。
伸びてくると、温度も水も控えめ。
大きくなると、どちらも厳しくします。
それ以外にも除草や、
表面を覆っているモミガラと稲藁の調整等をします。
追伸
昨日、「干し芋切甲セット」販売開始しました。
ご興味がある方は、干し芋のタツマのトップページからどうぞ。
干し芋のタツマ
直接ページはこちら
干し芋切甲セット2012
メロン畑
メロンに限らず、
畑や田んぼの土作りは、苗との兼ね合いになります。
メロンの苗の育ち具合に合わせて、
丁度畑の準備もできていました。
メロンは朝と夕方の最低2回は畑を回ります。
それ以外にも、天候や気候により、管理することがでてきます。
収穫まで家と畑を行き来する日々が始まります。
たかおさんのメロン苗
3月に種を植えたメロンの苗がだいぶ育っています。
3月から4月は例年よりも低い気温の日が多かったのですが、
4月終わりに畑を出すいつものスケジュールに間に合いそうです。
昨年はほとんど収穫ができないという、
今までに経験がない不作だったので、
今年こそは、順調に育って欲しいものです。
苗が出揃ってきました
人参芋を皮切りに、
いずみ、ホシキラリ、玉豊、紅あずまの苗の芽が出揃ってきました。
最後に玉乙女も目が出て今年は予定通りに進みそうです。
人参芋はたくさんの出荷依頼が来ているので、
一番条件が良いところに植えたせいもあり、
一番早くなおかつ順調に育っています。
健康な苗作りがサツマイモ栽培の第一歩です。
特に有機栽培では、
畑にだしても雑草に負けない苗は必須です。
ここからは時に優しく、
時に厳しく強い苗に育てていきます。