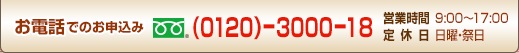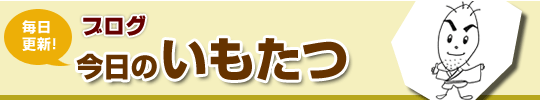- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
偉大なるアンバーソン家の人々 1942米 オーソン・ウェルズ
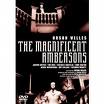
市民ケーンに続くオーソン・ウェルズ第二の作品で、
市民ケーン同様に商業的には失敗。
けれど当時から作品の評判はすこぶる高かったようです。
前作同様、凝った撮影と社会問題を取り上げています。
そして人間個人の性をもテーマにしていて、
たくさんの見どころがあります。
冒頭で、世の変化を上手く演出してその感覚で本編が
流れているようです。
家での舞踏会
クルマと馬車
変わってゆく街と街の人たち
そしてアンバーソン家はなかなか変われず
亡くなって行き、最後には・・・。
人は、大富豪でも天才発明家でも庶民でも
大きな中のひとつのギアとしては同じであること。
変化が必須でそれを肯定するものも、
否定すつものも、その流れを促す一員であること。
それも語られ、
オーゾン・ウェルズが、20代でそれを知り尽くして
表現していることも驚きです。
四十挺の拳銃 1957米 サミュエル・フラー
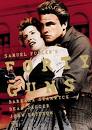
どんな人格者でも肉親に対して甘くなる。という
世俗的なテーマが背景ですが、
そこに留まらない展開があります。
敵役の姉弟の関係の問題は表面に、
味方役の兄弟の関係は隠れた問題を潜めています。
どちらも人に対して何ができているかを、承認して欲しい。
心の基本の問題です。
二つは悲劇になる、と、ならないに分かれます。
その原因は明らかです。
乱暴な言い方ですが、貧乏の方が
(この場合は恵まれすぎていない方が)
幸せが多いことです。(多いと個人的に感じています)
結局、目先の幸せは人が作り出した幻想かもしれません。
本心が望むものは?
それを埋めるために、無理をして幻想を作っているのが
現代かもしれません。
市民ケーン 1941米 オーソン・ウェルズ

市民の定義を定めることから、
この映画の鑑賞が始まります。
自分は凡人としての一市民だから、
市民です。ところが・・・。
を感じさせ、そこの物語の深さが(アメリカの当時の状況)、
この映画の評価のひとつになっていることがわかります。
この映画は他にも、脚本もカメラワークも大胆な構成も、
オーソン・ウェルズが当時25歳という現実も、
多くの評価対象が確かにありました。
けれど、市民を皮肉るような全体を制している空気が、
私としてはこの映画の魅力を感じました。
「薔薇のつぼみ」は微妙です。
見解が幅広いでしょう。
表向きもぼかされている上、
どうしても性的な、踏み込んだ理も考えてしまいます。
このあたりの妙が、これ以外にもちりばめられていることが、
金字塔としての評価を得ているこの映画の側面なのでしょう。
ハリケーン 1937米 ジョン・フォード

人には心があります。
これは身に付けたものではありません。
文明や法という言葉が台詞で、何度も出てきます。
それらとその価値観は、人が決めて身に付けたものです。
この物語は、脇役の総督が、それらの人としての
本来の心を取り戻す物語でもあります。
それを注目してしまうのは、
総督をみていて憤るのに、私が総督のように振舞うことがあることを、
示してくれているからです。
他の見所も満載です。
ハリケーンの壮絶な、年代を考えるとありえないほどの、
凄さと、リアルさ。
人種問題と植民地の現実の是非。
前述に関係ありますが、「法そのもの」そして、
法とは誰のため、何のためという問いかけ。
そして家族のもとへ、何が何でも帰る男。
演出も◎です。
初期部分の島や、前半の海と、
ハリケーン前後の海と島の様子も。
個人的に反省を促す、プラス
映画を楽しむとしてもおもしろい作品でした。
山河遥かなり 1947米 フレッド・ジンネマン

戦争の傷跡が、個々の子供に植え付けられている、
悲しく、深い傷が、冒頭でとつとつと語られているところから
物語がはじまります。
今までに感じることができなかった、気づかなかった戦争の影響を
目の当たりにされます。
それだけに、ラストは感動を呼ぶのですが。
アメリカが良く描かれすぎていると、
へそ曲がりにも感じてしまいますが、
当時のアメリカの自負がわかります。
時折映し出されるガレキとともに、まだ、この少年の年なら、
生きていても良いほど、大戦は近い過去だったことを改めて想いました。
レンブラント 描かれた人生 1936英 アレクサンダー・コルダ

自分の絵は、世界に影響をするとわかっていないはずですが、
そんな予感があったとしか説明のしようがありません。
それほど、絵に執着しています。
だけど、寂しくて、人恋しくて。
この脚本はどこまでが真実に近いかは誰もわかりませんが、
レンブラントの人となりを感じます。
時間が経って、本当の姿が(タイムマシンなどで)わかるまで、
作品から探るこの人となりは、確立されたひとつの描き方とつながります。
この映画が良い出来だと感じる点はまだあります。
成功するしないは別として、人生を登るときの圧倒さではなく、
下り坂からスタートしたこの映画は、
誰もが迷う人生の後半を先取りして示してくれています。特に内面を。
この映画に影響されて、偉大な画家の映画が造られたのもわかります。
当時の社会とそのかかわりを丁寧にみせてくれています。
「モンパルナスの灯」もそういえば、社会とのかかわりに
重きをおいていたことを思い出しました。
古い映画をさぐると、その原点に触れる偶然があります。
それもすばらしい出会いです。
海の沈黙 2004仏/白 ピエール・ブートロン
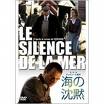
人は誰も誇りを持っています。
その尊厳を認めること。
仇敵の間でそれを認め合います。
物語には何もない抵抗があります。
大きな逆らえない中にいる将校(ただ立場は占領しているだけ)は、
あなた達を精一杯愛します。を続けます。
自分ができる範囲でしかないことを、わかり、悔やみながら。
心の琴線に“訴えかけてくれる”作品でした。
ラストに花を置くシーンがありました。
上手く行かないことを、力で、順序を追わず、
やってはいけない象徴なのですが、
これは、やってはいけないことを、
乗り越えて、やったのでしょう。
確信はないですが、
個人的には、ジャンヌが将校の意図をわかったことを
信じるしかありません。
けれど確信を持ちます。
どんな状況になろうとも、
「ゆるぎなさ」を将校とジャンヌが得たことを。
沈黙や静とは。
その強さや意味を語れることをできれば、
彼らは、生きてゆく意義をつかめたのではないでしょうか?
とても意義ある時間=こういうことを考える時間を
を過しました。
スパイダーマン 2002米 サム・ライミ
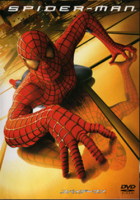
安心するために観る映画に映りました。
物語の展開が、「やっぱりこうでなくちゃ」という感じですね。
西部劇 水戸黄門説 を自論としているのですが、
これもその路線かな。
だから映画がどうのこうのというよりも
観たい人がみて楽しめたのかというのがポイントだし、
そこがどうかなって気になっていました。
ベニスに死す 1971伊・仏 ルキノ・ヴィスコンティ

映像でほとんどを語る映画です。
表情、動き、構図、景色、そして音楽。
「美」や「醜さ」や人の「苦」は何かを考える意図も
あるのでしょうけれど、
この映像を観てただただ感じるだけで良いような感覚で観ていました。
ついつい、意図を考えがちなのですが、
ただただ、鑑賞するそんな映画でした。
でもそこには、むなしさやはかなさを強く感じる内容です。
この物語の設定は奇異かもしれませんが、
時代やその社会や風習が違うだけです。
人が生きることは苦であることを前提にすると、
楽しめることは多いものです。
勝間和代現象を読み解く 日垣隆

モハメド・アリの姿が、読書中想像されてしかたありませんでした。
遠巻きにして急所を刺す!
世間知らずなので、
勝間さんのことをあまり知りませんが、
すごいキャリアとカリスマ性があることがわかります。
それとちょっと人間臭さもあるのでしょう。
日垣さんはフラットにクールに、
時折熱く、大人の感覚を持った人だと思っています。
その日垣さんの茶目っ気を感じる一冊でした。