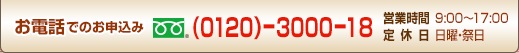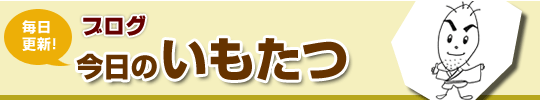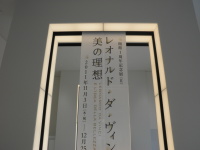- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
有機安納芋(九州産)
有機農産物を扱っている取引先から、
有機安納芋が送られてきました。
大きく育ちすぎたので、干し芋にできるか試して欲しい
という依頼です。
安納芋は自社でも有機栽培で少しですが、生産しています。
ここまで大きく育たないので、
流石、九州は気候が違うと驚いています。
安納芋を干し芋にする場合の問題点は作業性です。
自社の有機安納芋は、身崩れしてしまうのが難点です。
さて、九州宮崎産の有機安納芋はどんな感じでしょうか。
年末です
干し芋の出荷ピークは12月の今頃です。
今年は例年よりも少ない注文でしたが、
ここに来てバタバタです。
昨日はほしいも産地に行きましたが、とんぼ返りでした。
往復の新幹線は金曜日と重なってとても混雑。
大きいキャリーバッグも目立ちました。
そろそろ海外へ、ふるさとへ、ですね。
ほしいも農家及び関係者は、そんなのんびりする人達に
干し芋を届ける日々がもう少し続きます。
追伸
一昨日は「冬至」でした。二十四節気更新しました。
ご興味がある方は、干し芋のタツマのトップページからどうぞ。
干し芋のタツマ
二十四節気「冬至」の直接ページはこちら
冬至
干し場(平と丸)
すっかり冬の気候です。
干し場にも丸干し芋が目立つようになってきました。
丸干し芋をはじめタツマオリジナルの大判等
の特殊な、厳寒の時に加工する干し芋は冬本番の1月からですが、
それらを手がけ始めようかという感触の天候になってきています。
キュアリング
サツマイモを摂氏30℃湿度100%の中に
60時間以上おくと、保存性がとても良くなります。
この作業のことを「キュアリング」といいます。
干し芋農家は、蒸かすためにボイラーがありますから、
それを活用して、庭先でキュアリングをする家が多いです。
サツマイモをつんでおいて、厚いシートをかぶせて行います。
本来キュアリングは、専用の建屋の中で行いますが、
庭先でシートをかけて行うので、
「簡易キュアリング」と呼ばれています。
レオナルド・ダ・ヴィンチ美の理想展
レオナルド・ダ・ヴィンチが弟子達や、その後の絵画、
その当時の芸術家に与えた影響を、
様々な作品で探るという美術展でした。
彼は絵画を単なる芸術を超えたものとして
とらえていたそうです。
科学であり、哲学であり。
イタリアがまだ統一されていない時代背景も
垣間見ることができました。
何を持って絵を語るか、
絵に何を語らせるか、
そういう見方をしながらの鑑賞でした。
多くのモナ・リザと、
多くの裸のモナ・リザ。
「モナ・リザ」が持つ魅力(ダ・ヴィンチの偉大さ)
の現れです。
多くの関連作品は、彼を賞賛しています。
まだまだ知らない功績の一端に触れた時間でした。
深みの逸品
セブン&アイ専用のサントリーのプレミアムビールです。
モルツとは違う路線のプレミアムビールです。
棲み分けできそうな感じです。
私はこちらの方が好み。
アルコール度数6.5%の表示ですが。
そこまでの印象はありませんでした。
仰々しい薀蓄が書かれていますが、
それ相応の美味しさがありました。
山廃純米生原酒 23BY
かなり重要で、とても待ち遠しい年中行事です。
毎年菊姫酒造では、新酒の第一弾は、
「にごり酒」です。
それに続いての蔵出しが「山廃純米生原酒」です。
ただでさえ鮮烈な酒の山廃純米の
「生酒」「原酒」「無濾過」しかも出来たての搾りたて新酒です。
山廃純米とは別物といえる荒々しさがあります。
(でも紛れもない山廃純米が根底にあることを感じます)
さて今年、23BYは、
「強い酒」です。
純米酒の原酒ですからアルコール度数は19度、
いつも強さを感じますが、
23BYは顕著です。
のどを通ってからジワジワ強さを感じます。
旨味も相変わらず多く、酸味が強いのに濃さと甘みがあるので、
かなりの甘みです。
こういう酒は挑戦的ですから、
当分毎晩格闘が続く。
一口でそれを感じました。
銀幕倶楽部忘年会
映画を何千本も観ている猛者(大先輩)の方たちとの
忘年会でした。
昭和20年代後半の映画全盛期に、
リアルタイムで映画と過ごした皆様のお話は圧巻です。
その次世代の先輩方も負けず劣らずです。
リアルタイムとまでは行きませんが、
まだまだ映画館が(今のシネコンでとは違う)
残っていた時に映画少年少女時代を過ごし、
そのまま映画とともに生きた方々です。
ここ数年追いつけとばかり、沢山の映画を観ていたので、
会話での相槌くらいはできるものの、
まだまだ皆さんにはかないません。
一番かなわないと感じたのは映画を愛する心だと痛感しました。
止まれ!
農家から道路へ出る、農家の家の塀の内側のカンバンです。
自分で作ったカンバンではなく、
道路標識(のよう)です。
どうやって手に入れたか、
いつもこれを見ると聞いてみようと思います。
この農家ではありませんが、
なぜか、「高萩市」(茨城県北部の太平洋側の町)の
カンバン(標識)がある農家があります。
今は見慣れましたが、最初は驚きました。
初号アサヒビール復刻版
コクがあります。
旨味も甘みも苦味も控えめですが、
上品な味わいという感じです。
スーパードライのような
おどかされている味とは真反対です。
控えめと書きましたが、
薄いビールではありません。
しっかりしたビールです。
缶のデザインも味わい深いですね。
コストや意地や誇りをかけていることが
伝わってきます。